認知症になるといつまで自立して生活できる?認知症患者の自立度について解説

目次 [閉じる]
「認知症になると寝たきりになる」「家族の顔もわからなくなる」といったイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。実際には、こうした状態は認知症がかなり進行した段階で見られるものです。認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)や初期の認知症であれば、自立した生活を送っている人も多く、中には支援制度やサービスを活用しながら仕事を続けている方もいます。
今回の記事では、認知症と自立度の関係をわかりやすく解説し、認知症になってもできるだけ自立した暮らしを続けるために必要なポイントを紹介します。
認知症と「自立度」の関係を理解しよう
認知症というと「もの忘れがひどくなる」「徘徊するようになる」といったイメージがあるかもしれません。しかし、認知症の影響はそれだけにとどまりません。
脳は、私たちの日常生活のあらゆる行動を支える重要な役割を担っています。本や新聞を読む、買い物で必要なものを判断する、気候に合わせて服を選ぶなど、日常の当たり前の行動はすべて、脳の認知機能によって成り立っています。そのため、認知症になると、日常生活のさまざまな場面で影響があらわれるようになります。
さらに脳は、知的な活動だけでなく身体の機能も司っています。たとえば、くも膜下出血や脳梗塞が起きると、下半身不随などの身体に直接的な障害が現れることがあります。同じように、認知症による脳への影響は、認知機能だけでなく身体機能にも及ぶことがあります。
認知症の症状は進行度によって異なり、それに応じて「日常生活自立度」も変化します。自立度のランクが低い段階では、自分でできることが多く、ほとんど制限のない生活を送ることが可能です。一方で、自立度のランクが上がっていくと、日常の多くの場面で家族や介護者のサポートが欠かせなくなっていきます。
自立度の意味とその位置づけ
「日常生活自立度」とは、高齢者における障害や認知症の程度を段階(ランク)で示す指標のことです。これは、要介護度を正しく判断するための基礎となるものであり、その人にどの程度のケアが必要かを測る際に活用されます。
ここで注意したいのが、「要支援」や「要介護」といった区分とは異なる指標である点です。要支援・要介護は、介護サービスをどれくらいの時間・頻度で必要とするかという「介護の必要度」を示すものです。一方、自立度は「高齢による障害や認知症の進行度合い」を段階的にランク化し、本人の状態を表すものです。
つまり、「その人がどの程度、自分の力で生活を維持できるか」を示す指標になります。両者は混同しやすいため、「要介護=自立度」と思い込まないよう注意が必要です。
日常生活における自立度の目安
それでは、実際に自立度の目安について見ていきましょう。自立度のランクが低い状態をできるだけ保つことが、できる限り自分らしい生活を続けるための重要なポイントです。
前提として、認知症は進行段階によって自立度が変わっていきます。たとえば、認知症ではなく日常生活に支障がない場合は「自立」とされます。しかし認知症を発症すると、進行度に応じて少しずつ自立度のランクが上がっていき、サポートが必要になる場面が多くなっていきます。
65歳以上の認知症の高齢者における自立度は、大きく5つに分類されます。自立度ⅠからⅣまでは、生活動作への影響を基準に区分されており、ランクが上がるにつれて、着替えや食事、移動など日常生活の基本的な行動においても、他者からのサポートが必要になっていきます。
| ランク | 日常生活の目安 |
| 自立 | 日常生活に支障がなく、自活できている状態 |
| 自立度Ⅰ | 何らかの認知症を有しているが、日常生活の必要な意思の疎通ができ、ほぼ自立で一人暮らしが可能 |
| 自立度Ⅱ | 日常生活に支障が出るようなもの忘れなどの症状や、意思疎通のつまずきが見られるものの、誰かが注意していれば自立できる |
| 自立度Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの症状が見られ、たびたび道に迷う、買い物や金銭管理など、これまでできていたことにもミスが目立つようになる |
| 自立度Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの症状が見られるようになり、服薬管理や、電話や訪問者への対応などが難しくなる |
| 自立度Ⅲ | 日常生活に支障が出る症状や行動、意思疎通の困難さが認められ、日常生活の多くで介護を必要とする |
| 自立度Ⅲa | 日中を中心に上記Ⅲの症状が見られ、着替えや食事、排泄が上手くできなかったり、とまどったりするようになる 徘徊や失禁、異食などが見られることがある |
| 自立度Ⅲb | 夜間を中心に上記Ⅲ、上記Ⅲaの症状が見られる |
| 自立度Ⅳ | 頻繁に症状が見られるようになり、Ⅲの段階よりもより深刻な状態となり、日常生活で常に介護を必要とする |
| 自立度M | 日常生活に必要な意思疎通がむずかしくなる、または稀にしかできなくなり、せん妄や妄想など著しい精神症状や問題行動、重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |
認知症の進行と自立度の変化
ここからは、認知症の進行に伴ってあらわれる特徴的な症状と、それに応じた自立度の変化について見ていきましょう。
認知症の多くは進行性であり、症状はゆるやかに少しずつ進んでいきます。その進行に合わせて、自立度のランクも徐々に上がっていき、自分でできることは少しずつ減っていきます。
ただし、進行の速度には大きな個人差があります。そのため、同じ年齢で認知症と診断されていても、自立度の状態は人によって異なります。また、認知症になったからといって、すべての人が最終的に自立度Ⅳ、自立度Mの要介護の状態に至るわけではありません。なかには、自立度ⅠやⅡの状態を保ちながら天寿をまっとうする人もいます。
つまり、認知症だからといって「必ず要介護状態になる」というわけではないという点を理解しておくことが大切です。

画像素材:PIXTA初期の認知症:ほぼ自立して過ごせる時期(自立度Ⅰ~Ⅱ)
認知症の初期段階では「長く通院している病院の行き帰りで迷う」「頻繁に忘れ物や探し物を探している」といった症状が見られます。とはいえ、日常生活に大きな支障があるわけではなく、自立度としてはⅠ~Ⅱにあたります。
この段階では歯磨きや着替え、入浴といった基本的な生活動作は自分でこなすことができ、一人暮らしや仕事を続けている人も少なくありません。
また、適切なケアや治療を受けることで、症状の進行を緩やかにしたり、進行をある程度抑えることも期待できます。つまり、自立度Ⅰ~Ⅱの段階であれば、認知症を抱えていてもほぼ自立した生活を送ることが可能です。
中等度の認知症:部分的なサポートが必要になる時期(自立度Ⅱ~Ⅲ)
認知症が中等度まで進行すると、自立度のランクはⅡ~Ⅲに該当します。この頃になると、これまで問題なくできていた日常の行動に支障が出てきます。
たとえば「金銭管理や買い物を一人でやり遂げるのが難しくなる」「一人で留守番ができなくなる」など、自立した生活に必要な力が少しずつ失われていきます。また、気候に合った服装を選ぶ、決まった時間に薬を飲むといった自分自身の身の回りの管理も難しくなります。そのため、この段階まで進行すると、自立した生活を維持することが難しい状態になります。
さらに、個人差はありますが、徘徊や失禁といった症状が見られることもあり、訪問指導や訪問看護、デイケアなどの介護サービスが必要になる時期です。
後期の認知症:日常生活の多くでサポートが必要になる時期(自立度Ⅲ)
認知症がさらに進行して後期に入ると、自立度はⅢのレベルにあたり、自立して生活することは困難になります。この段階では、日常生活の多くの場面で家族や介護者によるサポートが必要になります。
また、長年連れ添った配偶者や、自分の子ども・親といった身近な人の顔を認識できなくなることもあります。歯磨きや着替えなどの基本的な生活動作も自力で行うのが難しくなり、介助を要する場面が増えていきます。
さらに、排せつをトイレ以外の場所でしてしまうことがあったり、入浴の際にも介助が必要になるだけでなく、入浴そのものを拒む場合もあります。そのため、この段階では介護する側の負担も大きくなりやすい時期です。
終末期の認知症:多くのことが自分でできなくなる時期(自立度Ⅳ)
認知症が終末期に至ると、認知機能は高度に障害され、自立度はⅣの状態まで進行します。
この頃になると、歩いたり座ったりといった基本的な動作も難しくなり、寝たきりで過ごす時間が多くなります。食事や排せつにも全面的な介助が必要となり、会話の回数や発する言葉の数も少なくなっていきます。
日常生活の多くのことを自分ではおこなうことができず、常に介護者による見守りとサポートが欠かせない状態となります。
認知症でも自立して生活できる期間を延ばすために必要なこと
現在、発症した認知症を完全に元の状態に治す治療法はありません。しかし、早期の認知症における認知機能の改善に向けたアプローチは、近年多くの研究や知見が集まりつつあります。そのため、認知症だからといって、必ずしも絶望する必要はありません。
実際、認知症の前段階とされる軽度認知障害(MCI)と診断された方のうち、4人に1人は健常な状態にまで改善したというデータもあり、初期の段階であれば適切なリハビリテーションや治療によって、認知機能が改善する事例も多く報告されています。
そのために重要なのは「早期発見・早期介入」です。「最近、もの忘れが増えた」「なんだか自分らしくない行動が増えた」といった小さな違和感を見逃さず、早期に専門機関でチェックすることが大切です。また、自分の変化に気づくための環境や体制を整えておくことも欠かせません。
これまで紹介したような症状が見られる場合でも、適切なケアや治療、そしてサポート体制を整えることで、周囲への負担を抑えながら自立度を保って生活を続けられる可能性があります。まだ受診していない方は、この機会に一度、専門の医療機関に相談してみることをおすすめします。

画像素材:PIXTA早期発見のための取り組み
日常生活の変化チェックリスト
ここからは、認知症をできるだけ早く見つけるための具体的な取り組みを紹介します。
まずは、日常生活の中で以下のような変化がないか、自分や家族でチェックしてみましょう。チェック項目の数に応じて、その後の対応が変わります。
- ATMや洗濯機などの機械操作でまごつく、あるいは以前より時間がかかる
- 待ち合わせの時間を勘違いする、あるいは待ち合わせ自体を忘れてしまうことが最近複数回あった
- さっき話したことを繰り返して話すことが度々ある
- 物を置き忘れたり、忘れ物を頻繁に探している
- 家にこもりがちで、外出が減っている
- 薬を飲み忘れたり、飲みすぎたりすることがある
- 以前より怒りっぽくなった、落ち込みやすくなったなど感情の起伏が激しくなった
- 以前より身だしなみに意識が向かなくなった
- 毎日のように、今何をしようとしていたか思い出せないことがある
チェック項目が2つ以上ある場合→「もの忘れ外来」など医療機関の受診を検討してください
チェック項目がほとんどない場合→状況に応じて、その他の取り組みを検討してください
チェック項目が2つ以上ある場合:早めの医療機関受診を検討
チェックリストで2つ以上の項目に当てはまった場合、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)や、認知症の兆候の可能性があります。こうした場合は、早めに医療機関を受診し、専門的な検査や治療を受けることが大切です。
チェックリストで3つ以上の項目に当てはまる場合は、認知症だけでなく、他の疾患が関係している可能性もあるため、できるだけ早めの受診をおすすめします。早期に受診することで、適切な治療やサポートにつなげ、自立した生活をできるだけ長く維持することが期待できます。
チェック項目がほとんどない場合①:認知症ドックでリスクを把握
チェックリストでほとんど当てはまる項目がない場合でも、「将来的に認知症になるリスクを知りたい」という方には、認知症ドックの受診をおすすめします。
「認知症ドック」は、認知症に特化した検査プログラムです。脳機能チェックや脳画像検査などを組み合わせることで、認知症の兆候や将来的なリスクがないか総合的に検査します。
受けられる医療機関が限られていることや、費用が高額になるケースもあるため、受診を検討する際は費用や内容を事前に確認しておくと安心です。
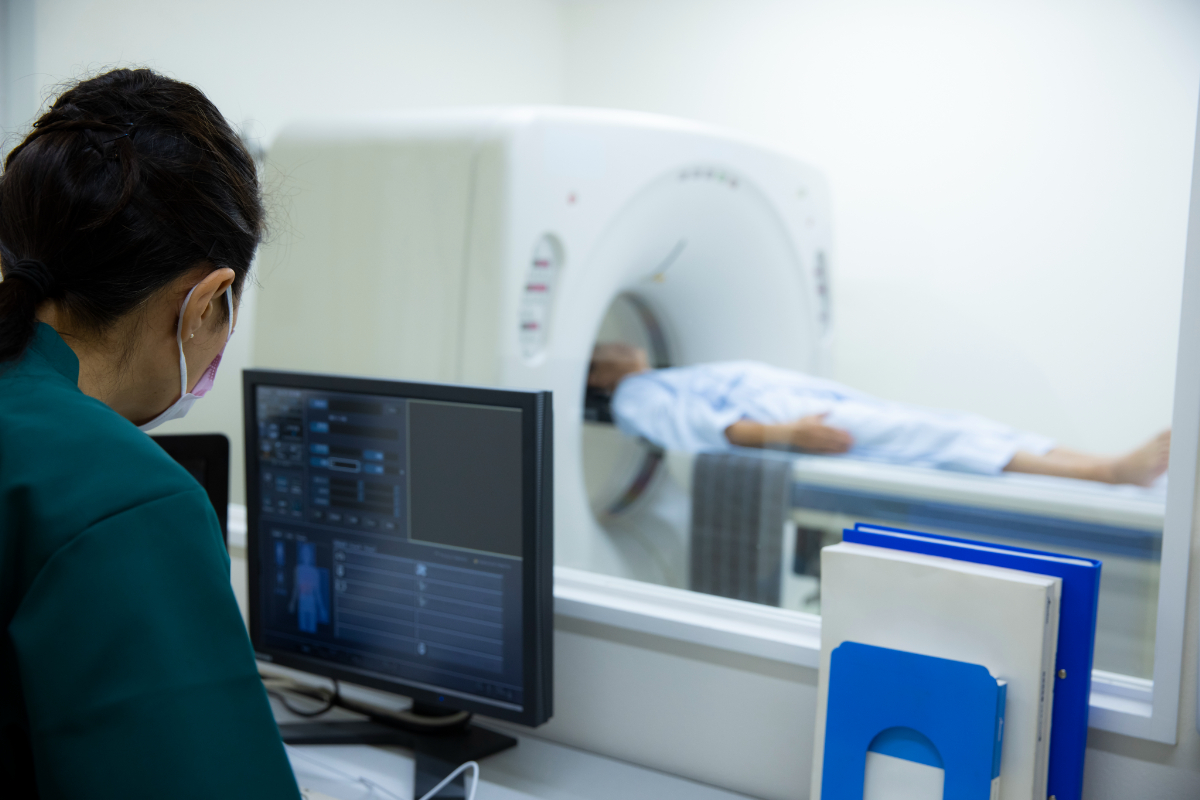
画像素材:PIXTAチェック項目がほとんどない場合②:FDG-PET検査でより詳細に確認
チェックリストでほとんど当てはまらない場合でも、認知症リスクをより詳細に確認したい方には、「FDG-PET検査」という選択肢もあります。
FDG-PET検査は、認知症の早期発見に役立つ脳画像検査です。特殊な薬剤を用いて脳の代謝を画像化することで、MRIやCTでは見えにくい脳の微細な変化を視覚的に確認することができます。そのため、初期段階のわずかな変化にも気づきやすいのが特徴です。
健康保険適用外のため受診料金が高額であることや、検査を受けられる施設が限られていることから、受診のハードルはやや高めですが、認知症をより早期に発見できる可能性を高める検査です。
当てはまる項目がほとんどない場合③:『認知症と向き合う365』で継続的にチェック
チェックリストでほとんど当てはまらない場合でも、手軽に認知症対策に取り組みたい方には『認知症と向き合う365』がおすすめです。
このサービスでは、脳の認知機能セルフチェックや、AIによるMRI画像の画像解析「BrainSuite®」を組み合わせ、認知症リスクの早期発見をサポートします。MRI画像検査は全国の提携医療機関で受けられ、心理士や医師など専門スタッフへの相談体制も整っているため、必要なときに専門的なサポートを受けられるのが特徴です。
また『認知症と向き合う365』は単発の検査や評価で終わらず、継続的にサポートを受けられる点も大きな魅力です。早期から自分の認知機能の変化に向き合い、必要に応じた介入やケアをおこなうことで、将来の自立した生活の維持にもつながります。
まとめ
今回の記事では、認知症患者の自立度について解説するとともに、認知症になっても自立して生活するために必要なことを紹介しました。
理想としては認知症にならないことですが、認知症は誰でもなる可能性があるものです。大切なのは、できるだけ早い段階で気づき、適切な対処につなげることです。早期の対応と正しい知識に基づくケアや生活習慣の工夫によって、症状の進行を抑えながら自立度を維持し、自分らしい生活を続けることが期待できます。
本ブログでは、認知症に関するさまざまな記事も掲載しています。ぜひ、認知症の知識を深め、自分や家族の備えに役立ててください。今日からはじめる取り組みが、将来の安心につながります。

画像素材:PIXTA- 画像素材:PIXTA
【参考文献(ウェブサイト)】
- 厚生労働省(n.d.). 要介護認定はどのように行われるか. [オンライン]. 2025年10月15日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html - 厚生労働省(n.d.). 認知症高齢者の日常生活自立度. [オンライン]. 2025年10月15日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077382.pdf - 日本神経学会(n.d.). 認知症疾患診療ガイドライン2017. [オンライン]. 2025年10月15日アクセス,
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html - 認知症と家族の会(2024). 認知症と向きあうあなたへ. [オンライン]. 2025年10月15日アクセス,
https://www.alzheimer.or.jp/?p=32277
【参考文献(書籍)】
- 秋下雅弘(2023). 目で見てわかる認知症の予防. 成美堂出版.
- 朝田隆(2025). 軽度認知障害(MCI)がわかる本. 講談社.
- 旭俊臣(2022). 早期発見+早期ケアで怖くない隠れ認知症. 幻冬舎.
- 佐藤俊彦(2015). 認知症の画像診断第一人者が語る ボケは止められる!. パプラボ.
この記事の監修者

佐藤俊彦 医師
福島県立医科大学卒業。日本医科大学付属第一病院、獨協医科大学病院、鷲谷病院での勤務を経て、1997年に「宇都宮セントラルクリニック」を開院。
最新の医療機器やAIをいち早く取り入れ、「画像診断」によるがんの超早期発見に注力、2003年には、栃木県内初のPET装置を導入し、県内初の会員制のメディカル倶楽部を創設。
新たに 2023年春には東京世田谷でも同様の画像診断センター「セントラルクリニック世田谷」を開院。
著書に『ステージ4でもあきらめない 代謝と栄養でがんに挑む』(幻冬舎)『一生病気にならない 免疫力のスイッチ』(PHP研究所)など多数。



