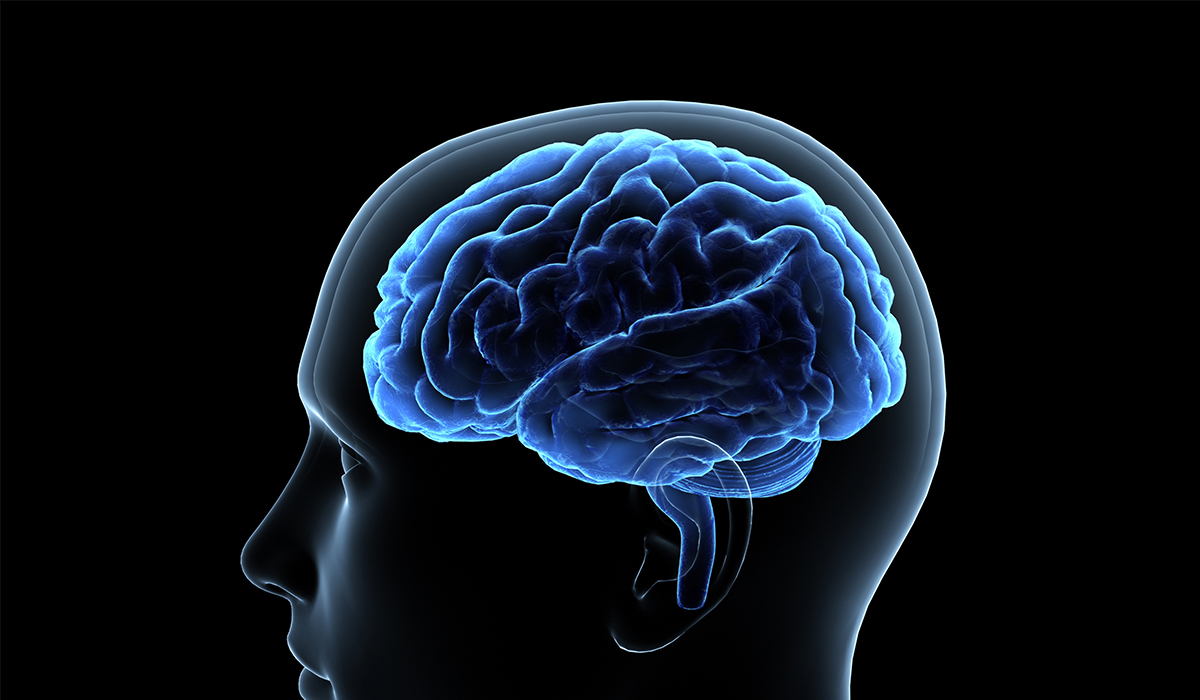50代によくある健康課題とは?今日からできる対策も解説

「人生50年」と言われていた時代はすでに過去のことになりました。現代は「人生100年時代」と呼ばれ、50代はまさに人生の折り返し地点にあたります。とはいえ、若い頃のように無理がきかず、体力や回復力の低下を感じる人が増えてきます。
さらに、これまでの生活習慣や働き方の影響が体に表れやすくなるのもこの年代の特徴です。その結果、日常生活や社会生活の中で、健康に関する課題に直面するケースも増えてきます。
今回は、50代によく見られる健康課題と、今日から取り入れられる具体的な対策についてわかりやすく解説します。
健康課題とは?
「健康課題」とは、私たちが生涯を通じて直面する可能性のある、健康維持や生活の質(QOL)に関わるさまざまな問題やリスクのことを指します。
日本は世界でも有数の長寿国であり、平均寿命は今もなお延び続けています。その一方で、日常生活を制限なく送れる期間を示す「健康寿命」との間には、平均でおよそ10年もの差があるのが現状です。この差によって、介護や医療への依存が増え、本人の生活の質が低下するだけでなく、社会全体にとっても大きな課題となっています。
こうした背景から、生活習慣病の予防や心身のケア、社会とのつながりの維持といった取り組みを通じて、健康課題にどう向き合うかがますます重要になってきています。
年代によって抱える健康課題は異なる
若くて元気なときには、「健康」というものをあまり意識していなかった方も多いのではないでしょうか。ところが、年齢を重ねると「寝ても疲れが取れない」「低下した意欲がなかなか戻らない」といった変化を実感し、健康を意識した生活の重要性が高まっていきます。
つまり、年齢に応じてどのように健康課題に向き合うかが、生活の質を左右する大きなポイントとなります。加齢による身体機能の衰えは自然な現象ですが、年代によって直面する健康課題の内容や深刻さは変化していきます。
また、健康状態は生活習慣や働き方、ストレス環境などにも左右されるため、同じ年齢であっても抱えている健康課題は人それぞれ異なります。
50代によくある健康課題
50代は、それまでの生活習慣の影響が目に見えるかたちで表れやすくなる年代です。高血圧や糖尿病といった生活習慣病をはじめ、脳梗塞などの脳血管障害のリスクも高まります。さらに、更年期による体調やホルモンバランスの変化も重なり、健康上のリスクが表面化しやすい時期でもあります。
だからこそ、これからの人生を健やかに過ごすためには、50代から健康課題に向き合い、具体的な対策を始めることが重要です。ここからは、50代で特に顕在化しやすい健康課題について紹介します。
50代によくある健康課題①生活習慣病
生活習慣病とは、その名のとおり「健康的とはいえない生活習慣」が大きく影響して発症する病気のことです。長年の喫煙や過度な飲酒、不規則な食生活や運動不足といった積み重ねの影響が、50代になるとはっきり表れてきます。そのため、50代は生活習慣病が一気に増えやすい時期ともいえるでしょう。
代表的なものとしては、糖尿病、高血圧、脂質異常症、メタボリックシンドロームなどがあります。これらは単独で健康を脅かすだけでなく、脳梗塞などの脳卒中や心臓病、さらには認知症の発症にも深く関わっていることがわかっています。
軽視すると重大な病気につながるおそれがあるため、早い段階から原因になる生活習慣の改善と予防に取り組むことが重要です。
50代によくある健康課題②骨・関節のトラブル
50歳前後になると、骨密度が少しずつ低下し始め、骨粗しょう症のリスクが高まります。特に女性では閉経の影響もあり、50代後半から有病率が一気に上昇する傾向が見られます。さらに、関節の滑膜に炎症が起こり、腫れや痛みを引き起こす「関節リウマチ」などのトラブルも増えてきます。
これまで大きな問題を感じていなかった骨や関節の不調が、この年代を境に一気に表れやすくなります。普段は意識することの少ない骨や関節ですが、私たちが立つ・歩く・動くといった基本的な活動を支える重要な役割を担っています。いわば「生活の土台」といえる存在です。
そのため、骨や関節に不調が生じると、痛みや不安が日常生活に影響を及ぼし、活動量や意欲の低下にもつながってしまいます。こうした負の連鎖を防ぐためにも、50代からは骨と関節の健康を意識した対策が不可欠です。

画像素材:PIXTA50代によくある健康課題③精神・心の健康
50代に入ると、多くの人が更年期を迎えます。更年期にはホルモンバランスの変化が起こり、自律神経の乱れや精神的な不調が生じやすくなります。その結果、精神面や心の健康に大きな影響が及ぶことがあります。
具体的には、特に理由がないのにイライラする、怒りっぽくなる、漠然とした不安が続くといった症状が表れることがあります。こうした状態が続くと意欲の低下につながり、対応が遅れるとうつ状態に移行するケースも少なくありません。
また、更年期障害は女性特有のものと考えられがちですが、実際には男性にも同様の症状が見られることがわかっています。女性の場合は閉経後5年ほどで症状が落ち着くとされる一方で、男性には明確な終わりの目安がないため、症状が長引いたり重症化するケースも見られます。
心身のバランスが揺らぎやすいこの時期は、精神の健康にもしっかりと目を向けることが重要です。
50代によくある健康課題④体重・代謝の変化
50代に入ると、更年期に伴う男性ホルモン・女性ホルモンの低下や、筋肉量の減少によって基礎代謝が下がりやすくなります。その結果、これまで以上に「太りやすく、痩せにくい」状態に変化していきます。
特に50代以降の肥満は、サルコペニア(筋力低下)や生活習慣病、心臓病などのリスクを高めることがわかっています。そのため、筋肉量を落とさずに適正体重を維持することが、将来的な健康を守る上で非常に重要です。
現在BMI25以上の肥満状態であれば、今後より痩せにくくなるため、早めに減量に向けた取り組みを始める必要があります。一方で、BMI18以下の痩せすぎも注意が必要です。筋肉量の低下に伴い低栄養やフレイル(虚弱状態)に陥りやすくなるため、過度に痩せすぎていることも健康に悪影響を及ぼします。
つまり、50代からは太りすぎも痩せすぎも避け、バランスのとれた体重管理がより不可欠になってきます。
50代によくある健康課題⑤歯周病の増加
40代を過ぎると、約2人に1人が4mm以上の歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)を抱えているといわれています。この歯周ポケットを放置すると歯周病が進行し、最悪の場合には歯を失う原因となる可能性があります。
さらに、歯周病は単なる口の中の問題にとどまりません。動脈硬化や誤嚥性肺炎など、加齢とともに増える全身の病気に関わっていることが明らかになっています。また、歯の残存本数が少ない人ほど認知症のリスクが高まりやすいという報告もあります。
歯の健康は生活の質を維持するうえで不可欠な要素のひとつです。実際に高齢になるほど「残っている歯の本数」が幸福度に影響するという調査もあり、歯が私たちの心身に及ぼす影響は決して小さくありません。
50代によくある健康課題⑥網膜剥離や緑内障などの目の病気の増加
40代ごろから老眼がはじまり、50代に入ると目の老化が一段と進んでくるのを実感する方も多いでしょう。そうした中で増えてくるのが、網膜剥離や緑内障といった深刻な目の病気です。特に緑内障は、日本における失明原因の第一位とされており、対応が遅れると失明につながる危険性があります。
また、それまで放置してきた目の違和感や軽い症状が、この年代になって一気に深刻化することも少なくありません。視野に影が見えたり、光がちらつく、ものが見えにくいなどの変化を感じたら、早めに眼科を受診して相談することが重要です。
人は得る情報のおよそ8割を視覚に頼っているといわれています。つまり「見え方」は生活の質そのものを大きく左右する要素です。50代からはこれまで以上に、目の健康を守るための取り組みを意識していく必要があります。
50代によくある健康課題⑦聴力の低下
50代になると、聴力の衰えを自覚する方が増えてきます。特に高音域から聞こえにくくなることが多く、日常生活で「聞き取りづらい」と感じる場面が増える人も少なくありません。
意外に感じるかもしれませんが、難聴は認知症の発症リスクを最も高める要因とされています。しかし、難聴を自覚しながら補聴器を利用している人は全体の約15%にとどまり、多くは放置されているのが現状です。聞こえづらさを放置すると認知症リスクが高まるだけでなく、難聴のさらなる悪化につながる可能性もあります。
たとえば、人との会話が聞き取りにくくなった、テレビやスマートフォンの音量を以前より大きくしている、映画館で音が小さく感じる、といった変化がある場合は、早めに耳鼻科で診察を受けることをおすすめします。特に聴力低下は自覚しにくいことが多いため、違和感を覚えたらすぐに相談することが、早期対応・予防につながる重要な一歩です。

画像素材:PIXTA50代によくある健康課題⑧脳・認知機能の低下
50代になると、「物覚えが悪くなった」「もの忘れが増えた」と感じる方も少なくないでしょう。これは加齢に伴う脳の老化が一因で、記憶力や判断力などの認知機能が低下するのは自然な老化現象のひとつでもあります。
しかし、認知機能の低下はストレスやうつ状態、睡眠不足などでも起こることがわかっており、忙しくなりがちな50代の生活では避けがたい面もあります。とはいえ、これらを軽視すると健康全般に悪影響が出やすくなるため注意が必要です。
一方で、脳は使い続けることで成長や活性化が期待できることも明らかになっています。加齢に伴う認知症リスクは徐々に高まるため、今のうちから脳の健康に気を配り、心身のコンディションを整えながら脳を活性化させる取り組みをおこなうことが、将来の健康維持につながります。
健康課題と認知症の関係
認知症は加齢とともにリスクが高まる病気であり、将来的な生活の質にも大きく影響します。さらに、生活習慣病や心身の不調といった50代に増えやすい健康課題とも関わっていることから、この年代から意識しておくことが重要です。
さまざまな研究から、認知症のリスクには、生活習慣が大きく影響することが明らかになっています。50代は、これまでの生活習慣の積み重ねが健康課題として表れやすい年代でもあります。そのため、生活習慣や体調の問題に早い段階から適切に向き合うことが、認知症予防にも直結します。
一方で、健康課題を軽視すると問題が深刻化し、同時に認知症リスクも高まってしまいます。50代のうちから意識的に健康課題に取り組むことが、将来の心身の健康を守る大きなポイントとなります。
50代からはじめる認知症対策
認知症予防は、若いころのダイエットのように短期間で成果を求めるものではありません。大切なのは、長期的に続けられる習慣を身につけ、リスクを長期的に抑えていくことです。つまり、「一時的にがんばる」のではなく、日常生活の中で無理なく取り入れられる方法を継続することが重要です。
ここからは、認知症予防にも効果的とされる具体的な取り組みをいくつか紹介していきます。
運動習慣をつける
年齢を重ねると、筋肉こそが「財産」ともいえる重要な要素になります。筋力を維持することは、将来的なフレイル(虚弱化)やサルコペニア(筋力低下)の予防につながるだけでなく、寝たきりを防ぐうえでも欠かせません。
さらに運動は、筋力や体力の維持に加えて、ストレス解消や精神的な安定、さらには認知機能の維持にも効果があることがわかっています。
とはいえ、普段運動習慣がない人が急にハードな運動を始めるとケガのリスクが高まります。そこでまずおすすめなのは、1日の歩数を増やすことです。ウォーキングは筋力維持やストレス解消に効果的で、特に1日8,000歩程度歩くと健康へのポジティブな影響が大きいといわれています。ただし、いきなり高い目標を立てず、まずは「1日1,000歩増やす」「いつもより10分歩く」といった小さな目標からはじめることが継続のコツです。
運動習慣が身についてきたら、ランニングやジムでの筋トレなど、少し負荷のかかる運動にチャレンジしてみましょう。運動の種類は自由で、興味のあるものを選ぶことが長続きのポイントです。水泳やヨガ、自転車など全身を使う運動、あるいはダンスや乗馬などこれまで体験したことのない運動もおすすめです。
厚生労働省の推奨基準では、週に60分以上の運動を目安としています。まずは無理なく「ゆるく、毎日少しずつ」を意識して、運動を習慣化していきましょう。

画像素材:PIXTA禁煙にチャレンジする
喫煙は健康への良い影響がほとんどなく、肺がんや脳血管障害、認知症など多くの病気のリスクを高めることが知られています。そのため、健康を守るためには、できるだけ早く禁煙に取り組むことが重要です。
とはいえ、喫煙はストレス解消や気分転換、コミュニケーションの手段として習慣化している人も多く、やめにくいのも事実です。また、過去に禁煙に挑戦して失敗した人も少なくないでしょう。
大切なのは、目標を高く設定しすぎず、小さなステップから始めることです。たとえば「今日は1日禁煙してみる」といった短い期間での挑戦でも、禁煙を習慣化する第一歩になります。
もし禁煙中にどうしても吸いたくなる、集中できない、イライラするといった禁断症状(離脱症状)があらわれた場合には、ニコチンガムなどの喫煙補助製品を活用したり、禁煙外来など専門家のサポートを受けることもおすすめです。小さなステップを積み重ねながら、無理なく禁煙にチャレンジしてみましょう。
飲酒は適量を守って楽しむ
飲酒は楽しみ方が多く、趣味やストレス解消の手段として習慣化している人も少なくありません。しかし、アルコールの長期的・多量の摂取は無視できないリスクを伴います。
多量のアルコールを摂り続けると、胃や肝臓などの消化器官だけでなく、心臓や脳など全身の臓器にダメージを与える可能性があります。さらに、アルコール依存症や認知症のリスクを高めるだけでなく、糖尿病や高血圧などの生活習慣病にもつながることが知られています。
そのため、飲酒は1日あたり純アルコール20g(ビール中瓶1本程度)を目安に、適量を守って楽しむことが大切です。また、週に1日の休肝日を設けたり、特に飲む必要を感じない日はお酒を控えるなど、「飲まない日」を増やす工夫も効果的です。「飲まなくてよいときは無理に飲まない」ことも、健康を守るためのひとつの習慣です。
食事バランスの見直し
食事は私たちの身体の健康を支える基本であり、認知症予防の観点からも欠かせません。
50代になると、仕事や家庭の忙しさ、付き合いなどで外食が増えることもあるでしょう。しかし、基礎代謝が低下しているため、若いころと同じ食事内容では体重が増えやすくなります。そこで、カロリーを抑えつつ、タンパク質を意識して摂り、必要な栄養素をバランスよく摂ることを心がけましょう。
また、栄養補助としてサプリメントを利用している人もいるかもしれません。ただし、サプリメントは万能ではなく、不足しがちな栄養を補う程度なら役立ちますが、過剰摂取は健康に悪影響を及ぼすこともあります。利用する際は、薬剤師や登録販売者に相談し、適切に活用することが大切です。
定期健診の受診
50代になると、歯周病の増加や網膜剥離・緑内障などの目のトラブル、さらには聴力の低下といった症状が表れやすくなります。そのため、定期的に医療機関で健診を受けることが重要です。
目安としては、歯科は3か月に1回、眼科や耳鼻科は年に1回の受診が望ましいとされています。これらの病気は、早期発見・早期対応によって経過が大きく改善することが多く、定期健診を習慣化することが健康維持の鍵になります。
また「今は問題がないから大丈夫」と思っても、受診をやめてはいけません。定期的なチェックを続けることで、将来の健康リスクを未然に防ぐことにつながります。

画像素材:PIXTA『認知症と向き合う365』の活用
脳は、記憶力や判断力といった認知機能だけでなく、歩行や呼吸などの基本的な運動機能まで担う、生活の基盤となる器官です。しかし、その健康状態を日常的に確認する手段は限られています。そのため、習慣的な健康課題への取り組みに加えて、定期的に脳の健康状態をチェックすることがおすすめです。
『認知症と向き合う365』では、脳の健康状態を測るバロメーターのひとつである認知機能をセルフチェックできるツールに加え、MRI画像をAIが解析する「BrainSuite®」がセットになっています。これにより、定期的に脳の状態をチェックでき、小さな変化にも早く気づきやすくなります。
さらに、医師や心理士などの専門スタッフに直接相談できるフォロー体制も備わっており、脳の健康について不安や疑問が生じたときに安心して頼れる点もおすすめのポイントです。
まとめ
今回は、50代に多い健康課題と認知症リスクとの関係、そして今日から始められる具体的な対策を紹介しました。
50代は人生の折り返し地点です。これまでの生活習慣の影響が顕著になり、さまざまな健康課題があらわれる年代でもあります。だからこそ、早めに健康課題に向き合い、適切に対処することが、これからの人生をより充実して生きるための大切な一歩となります。
重要なのは、完璧を目指すことではなく、できることから少しずつ取り組み、地道に習慣化していくことです。今日から始められる小さな取り組みの積み重ねが、将来の健康や生活の質にポジティブな影響を与えます。今できることを大切に、無理なく取り組んでいきましょう。
- 画像素材:PIXTA
【参考文献(ウェブサイト)】
- いいほね.jp(n.d.). 年齢とともに増加する骨粗しょう症. [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://iihone.jp/cause.html - 厚生労働省(2024). 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023. [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf - 小林製薬 命の母(n.d.). その『関節痛』『筋肉痛』更年期が原因かも?原因と対処法. [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://www.kobayashi.co.jp/brand/inochinohaha/kounenki/arthralgia.html - 日本眼科医会(n.d.). 飛蚊症と網膜剥離 なぜ?どうするの. [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://www.gankaikai.or.jp/health/38/index.html - 日本呼吸器学会(n.d.). 禁煙のすすめ. [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://www.jrs.or.jp/citizen/nosmoking/think/method.html - 日本生活習慣病予防協会(2022). 日本の女性のやせ過ぎ問題とその栄養対策 Part 2 高齢女性のやせ過ぎ問題も待ったなし!. [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://seikatsusyukanbyo.com/calendar/2022/010665.php - 日本内分泌学会(2024). 男性更年期障害(加齢性腺機能低下症、LOH症候群). [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=71 - 日本補聴器工業会(2022). JapanTrak 2022 調査報告. [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://hochouki.com/business/report/program.html - 日本リウマチ財団(n.d.). 関節リウマチ. [オンライン]. 2025年9月26日アクセス,
https://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/rheuma/
【参考文献(書籍)】
- 北原逸美/ながさき一生(2025). 認知症の教科書増補改訂版. ニュートン.
- 長尾和宏(2023). コロナと認知症~進行を止めるために今日からできること~. ブックマン
この記事の監修者

佐藤俊彦 医師
福島県立医科大学卒業。日本医科大学付属第一病院、獨協医科大学病院、鷲谷病院での勤務を経て、1997年に「宇都宮セントラルクリニック」を開院。
最新の医療機器やAIをいち早く取り入れ、「画像診断」によるがんの超早期発見に注力、2003年には、栃木県内初のPET装置を導入し、県内初の会員制のメディカル倶楽部を創設。
新たに 2023年春には東京世田谷でも同様の画像診断センター「セントラルクリニック世田谷」を開院。
著書に『ステージ4でもあきらめない 代謝と栄養でがんに挑む』(幻冬舎)『一生病気にならない 免疫力のスイッチ』(PHP研究所)など多数。