脳の老化を防止するためには?認知症との関係性についても解説

目次 [閉じる]
人は生まれてから死を迎えるまで、常に変化を続けています。子どもから大人へと成長していく過程では、その変化は「発達」や「成長」と呼ばれ、前向きにとらえられます。一方で、成熟期を過ぎると、変化は次第に「老化」としてあらわれ始めます。これは誰にとっても避けられない自然な流れです。
年齢を重ねること自体を止めることはできませんが、「できるだけ若々しくありたい」「いつまでも健康でいたい」と願う方は多いのではないでしょうか。実際に、運動を習慣にしたり、食生活を見直したりと、アンチエイジングに取り組む方も増えています。
しかし、そうした状況でも意外と見落とされがちなのが、「脳の老化」です。脳もまた身体の一部であり、年齢とともに確実に変化していきます。そして、脳の老化が進むと、もの忘れや判断力の衰えなど、さまざまな変化があらわれるようになります。
そこで今回の記事では、脳の老化とはどのようなものなのかを説明するとともに、老化を防止するためのポイントや、認知症との関係性についても紹介していきます。
脳の老化とはどのようなものか
年齢を重ねるにつれて、「体力が続かない」「なんとなく体がだるい」といった身体の変化を感じる方も多いのではないでしょうか。こうした身体の衰えは、日々の生活の中で比較的わかりやすく実感できるものです。
一方で、脳の老化は目に見えにくく、本人が自覚しにくいという特徴があります。しかし、実際には脳も身体と同じように、年齢とともに少しずつ老化が進んでいきます。
脳の体積は、生涯を通じて変化し続けます。一般的には20歳前後でピークを迎えるとされており、その後は加齢とともに徐々に減少していきます。この減少の背景には、脳の神経細胞の死滅があります。神経細胞が少しずつ失われていくことで、脳全体が徐々に萎縮していきます。これが脳の老化と呼ばれる現象です。
脳の萎縮は、早ければ30代頃から始まり、65歳前後になると脳画像検査でも確認できるようになるといわれています。

脳の老化と認知症の関係
脳の老化によって脳が萎縮すると、記憶力や判断力・注意力といった「認知機能」が少しずつ低下していきます。こうした変化が進行すると、将来的に認知症へとつながる可能性もあります。ただし、「脳が萎縮した=認知症」ではないことに注意が必要です。
認知症とは、ある特定の病気を指す言葉ではなく、「脳の病気やトラブルによって認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたしている状態」の総称です。
つまり、脳が萎縮していても、それによって生活に支障が出ていなければ認知症とは診断されません。加齢にともなう脳の萎縮は自然な老化であり、多くの場合、認知症を引き起こすほどの深刻な認知機能の低下には至らないと考えられています。
また、認知症は脳の萎縮だけが原因で起こるわけではありません。たとえば、脳出血や脳梗塞といった脳血管障害や、異常たんぱく質の蓄積など、さまざまな要因によって引き起こされます。そのため、「脳が萎縮したから認知症になる」といった誤解には注意が必要です。
脳が老化する原因
脳の老化、つまり脳の体積が減少して萎縮が進んでいく現象には、さまざまな原因があります。なかでも、近年の研究では脳の萎縮と生活習慣との深い関係が指摘されています。
ここでは、脳の老化を招く代表的な原因を紹介します。
加齢
脳では、毎日およそ10万個もの神経細胞が死滅しているともいわれています。この神経細胞の減少によって、脳の体積は年齢とともに少しずつ小さくなっていきます。つまり、歳を重ねることによって、脳はじわじわと減少していくのです。
しかし、脳の容量自体を増やすことはできなくても、脳細胞に適切な刺激を与えることにより、脳の機能は向上し続けるということもわかってきています。たとえば、新しいことを学ぶ、運動する、読書や会話を楽しむなどの行動を積み重ねることで、脳の特定の領域が活性化されると考えられています。
逆にいえば、あまり使っていない脳の領域ほど、加齢とともに衰えやすくなるとされています。加齢そのものは避けられませんが、脳に適度な刺激を与え続けることで脳機能を維持することは十分に可能です。
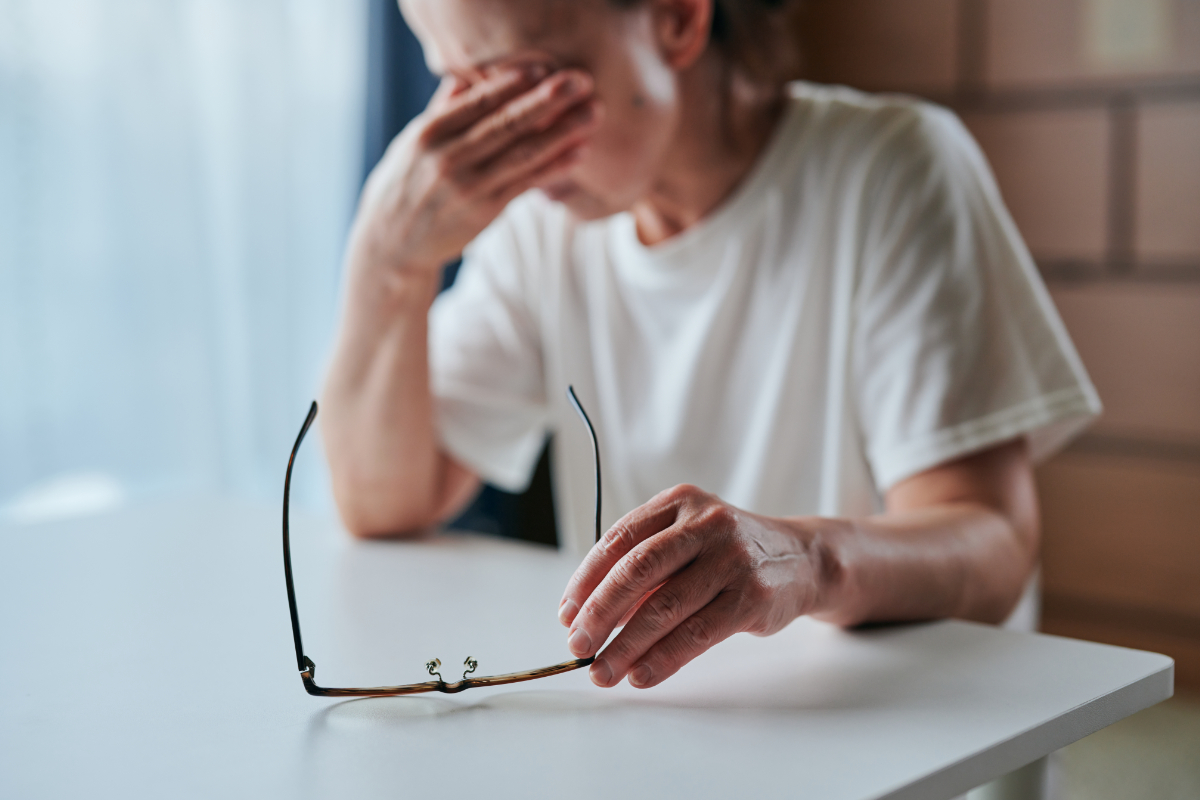
画像素材:PIXTA生活習慣の乱れ
「脳の老化」と聞くと、加齢による自然な現象のように思われがちですが、実は日々の習慣によって進行のスピードが大きく変わることがこれまでの研究から示されています。
なかでも、以下のような生活習慣は脳の萎縮スピードを進める原因となります。
- 栄養バランスの偏った食生活
- 長期間の喫煙
- 1日あたり缶ビール1本以上の飲酒
- 睡眠時間が短すぎる、または長すぎる
こうした状態が続くことで、脳への血流が悪化するなどの悪影響が生じ、結果的に脳の萎縮を早めてしまうことがあるので注意が必要です。
運動不足
運動不足が続くと血流が低下し、脳に酸素や栄養が届きにくくなります。その結果、脳の働きが鈍くなり、老化が進む要因となります。
さらに、運動不足は高血圧や糖尿病などの生活習慣病を招き、それが脳の血流をさらに悪化させる原因にもなります。近年の研究では、運動不足によって萎縮した筋肉から「ヘモペキシン」という物質が分泌され、これが神経の炎症を引き起こし、認知機能の低下につながる可能性があることもわかっています。
運動不足を放置していると、自分では気づかないうちに脳の機能が低下し、老化が進行してしまうおそれがあります。
社会的な孤立
少し意外に感じるかもしれませんが、「人との関わりの少なさ」も脳の老化を進める要因のひとつとされています。
日常のなかで人と会話を交わしたり、相手の表情を読み取ったりすることは脳のさまざまな領域を使うので、脳にとって重要な刺激になります。こうしたコミュニケーションが減ると、脳の広い範囲が十分に使われなくなり、機能が徐々に低下していくと考えられています。
また、社会的孤立によって感じるストレスや孤独感も、脳にとっては大きな負担となります。慢性的なストレス状態は、脳の神経細胞の働きを鈍らせ、老化を加速させる原因にもなりかねません。
人とのつながりが減っていくことで、脳の働きは少しずつ鈍り、気づいたときには取り戻せない変化へと進んでしまっていることもあるため注意が必要です。
脳の老化によって起こる症状
脳の老化は、脳全体で均一に起こるわけではありません。特に、大脳皮質の前頭葉や側頭葉と呼ばれる部分から、老化が始まりやすいといわれています。
この前頭葉や側頭葉は、記憶・判断・計画・会話など、日常生活に欠かせない認知機能を担う重要な役割を持つ部位です。そのため、これらの部位が衰えることで、さまざまな変化があらわれてきます。
ここでは、脳の老化によってみられる代表的な症状を紹介します。
もの忘れが増える
年齢を重ねるにつれて、「もの忘れが増えた」「新しいことが覚えにくくなった」と感じることが多くなります。
脳の記憶には、一時的に情報を保存する「短期記憶」と、長期間保存される「長期記憶」があります。脳の老化が進むと、特に短期記憶が衰えやすくなり、「今やろうとしていたことを忘れる」「買い物に行って目的の物を忘れる」などの場面が増えてきます。
判断力や理解力が落ちる
脳の老化は、思考力や判断力にも影響を及ぼします。
たとえば、寒い日に薄着で出かけたり、天気に合わない服装を選んだりといった行動がみられることがあります。また、新聞や映画の内容を理解しにくくなったと感じる場合も、脳の働きの低下が関係している可能性があります。
意欲が低下する
脳の老化が進むと、「やる気が出ない」「なんとなく何もしたくない」といった感覚が続くことがあります。
脳の前頭前野が衰えると「面倒だ」と感じやすくなり、何ごとにも消極的になる傾向が強まります。本人の性格の問題と捉えられることが多いですが、実は脳の老化による変化であることも少なくありません。

画像素材:PIXTA言葉が出にくくなる
「言いたい言葉が出てこない」「同じ言葉ばかり使ってしまう」といった変化も、脳の老化によってあらわれやすくなります。
特に、普段あまり使わない言葉は思い出しにくいものですが、「あれ」「それ」などの指示語で会話を済ませる場面が増えてきます。こうした言語のもたつきは、加齢とともに誰にでも起こり得ますが、脳の老化が進むとその頻度や程度が目立つようになってきます。
脳の老化防止が期待できる方法
身体機能と同じように、脳も年齢とともに自然に老化していきます。残念ながら、脳の老化を完全に防ぐことはできません。しかし、脳の老化をゆるやかにする方法はいくつもあります。
また、近年の研究では、脳は年齢に関係なく「使えば鍛えられる」ことも明らかになってきています。大切なのは、自分の脳の使い方のクセを知り、意識的に生活を見直すことです。そして、普段あまり使っていない脳の機能を積極的に刺激して鍛えていくことで、老化を防ぐ効果に期待できます。
ここでは、はじめやすい脳の老化防止法をご紹介します。
栄養バランスのとれた食事を意識する
脳の健康には、毎日の食事が大きく影響します。バランスよく多様な食品をとることで、脳の老化を防ぐ効果が期待できるでしょう。
たとえば、野菜を1日に150グラム以上摂る人は、ほとんど野菜を摂らない人に比べて老化による認知機能の低下がゆるやかであることがわかっています。また、青魚に多く含まれるDHAやEPAといった不飽和脂肪酸を摂取することも、脳の健康維持に有効とされています。
日々の食生活の見直しが、脳の健康を守る大きな助けになります。
十分な睡眠をとる
睡眠は、脳の回復と整理に欠かせない時間です。睡眠時間が短すぎたり長すぎたりすると、脳の老化を早めるおそれがあります。
研究によれば、6〜8時間程度の睡眠が脳の健康維持には理想的とされています。また、睡眠の質も重要で、寝る時間を一定にする、就寝前の食事を控える、強い光を避けるといった工夫が、質の良い睡眠につながります。
疲れが抜けにくくなったと感じたら、まずは睡眠習慣の見直しから始めてみましょう。

画像素材:PIXTA適度な運動を習慣にする
運動には、脳の活性化やストレスの軽減、生活習慣病の予防など、さまざまな効果があります。
1回20〜30分程度の散歩を週2回以上おこなうだけでも、脳への血流が改善され、老化の進行を抑える効果が期待できます。さらに、筋肉から分泌される「マイオカイン」という物質には、認知機能の維持にも関わる働きがあるとされています。
新しいことにチャレンジすることで脳に新たな刺激を与えることができるため、経験したことのない運動をはじめてみるのもおすすめです。
人との会話を大切にする
人と話すことは、脳にとって非常に良い刺激になります。会話では、言葉を選び、相手の意図をくみ取り、自分の考えを組み立てるといった複雑な処理がおこなわれており、多くの脳領域が活発に使われています。
日常的に誰かと会話をするだけでも、脳の働きを維持するのに役立ちます。家族や友人とのおしゃべりだけではなく、地域のコミュニティ活動など、外とのつながりを意識的に増やすことが大切です。
特に、一人暮らしの方は意識的に「人と話す機会」をつくることが脳の老化防止につながります。
脳の老化を感じたらどうすればいい?
脳の老化は誰にでも起こる自然な現象であり、日常生活に支障がない程度であれば過度に心配する必要はありません。ですが、将来の脳の健康を守るためには、脳の老化を進める生活習慣がないか見直し、できることから改善していくことが大切です。
また、「最近もの忘れが増えた」「普段しないようなミスが続く」「思い出せないことが増えて不安」といった状況がみられる場合は、念のため専門医に相談してみましょう。日常生活や仕事に影響が出ている場合は、認知症の初期症状の可能性もあるため注意が必要です。
「もの忘れ外来」などの専門外来では、医師が記憶や判断力の状態を客観的に評価し、必要に応じたアドバイスや治療につなげてくれます。早めに相談することで、不安を軽減できるだけではなく、症状の進行を遅らせるサポートにつながることもあります。
気になる変化がある場合は、「まだ大丈夫」と思い込まず、できるだけ早めに専門家に相談しておくことが安心につながります。
脳の老化防止に関するよくある質問
脳の老化防止が期待できる食べ物はありますか?
特定の食品を摂れば脳の老化が防げる、という特効薬のような食品は存在しません。しかし、毎日の食事内容を見直すことで、脳の健康を保ちやすくなることがわかっています。
特に大事なのは、「できるだけ多種類の食品をバランスよく摂ること」です。食事の偏りを防ぎ、脳に必要な栄養をしっかり届けることで老化防止につながります。
以下のポイントを意識して、毎日の食事を少しずつ見直してみましょう。
- 多種類の野菜を、できれば毎食摂るようにする
- 動物性脂肪(バター・生クリームなど)は控えめにする
- 不飽和脂肪酸(オリーブオイル・えごま油など)を積極的に摂る
- 魚や肉などのたんぱく質を一日一回は摂取する
- 主食・主菜・副菜のバランスを意識して食べる

画像素材:PIXTA脳の老化を防止できるサプリメントはありますか?
サプリメントだけで脳の老化を完全に防げるわけではありませんが、脳の健康を支える手助けとして上手に取り入れる方は増えています。特に、加齢にともない不足しやすい栄養素を意識的に補うことは、脳の健やかな働きを支える一助になる可能性があるとされています。
たとえば、DHAやEPA、ビタミンB群、ビタミンE、ポリフェノールなどは、脳の健康維持に関係がある栄養素として注目されています。こうした栄養素は食事だけで十分にとるのが難しい場合もあるため、サプリメントで補うのもひとつの方法です。
また、近年注目されているのが、水素を含むサプリメントです。水素には、体内で過剰になった活性酸素(ヒドロキシルラジカルなど)を除去する抗酸化作用があるとされており、酸化ストレスの軽減に役立つ可能性が指摘されています。動物実験や一部の研究では、水素水や水素吸入が脳内の神経細胞の損傷を抑えたり、認知機能の維持に寄与したりする結果も報告されています。ただし、ヒトに対する明確な効果については、現在も研究が進められている段階であり、万人に有効とは限りません。
この他にも、プラズマローゲンやバコパサポニン、イチョウ葉エキスなど、記憶力や認知機能に関する研究が行われている成分もあります。こうしたサプリメントを取り入れる際には、ご自身の体調や目的に合ったものを選ぶことが大切です。
なお、サプリメントはあくまで日常の栄養補助を目的としたものであり、その実感には個人差があります。摂取を検討する際は、医師や薬剤師、管理栄養士などの専門家に相談し、無理のない範囲で取り入れていくのが安心です。
脳の老化が早い人がよく使う言葉はありますか?
脳の老化が進むと、語彙がうまく引き出せなくなり、「あれ」「これ」「それ」などの指示語で済ませてしまう会話が増える傾向があります。
こうした言葉遣いの変化の頻度が高くなり、以前より語彙が極端に乏しくなってきたと感じる場合は、認知症のサインが隠れている可能性もあるため注意が必要です。気になる変化がよくみられるようになったときは、早めに専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
今回の記事では、脳の老化とは何か、その原因やあらわれやすい症状、そして老化の防止に期待できる方法について解説しました。
脳の老化は年齢とともに誰にでも起こるものですが、生活習慣や環境の影響によって進行のスピードは大きく変わります。食事・睡眠・運動・人との関わりといった日常の積み重ねが、脳の健康を守る大きな鍵となります。
また、脳の老化が進むことで、もの忘れや意欲の低下といった変化が起こりやすくなり、放っておくと認知症のリスクを高めてしまうこともあります。だからこそ、できるだけ早いうちから自分の脳の状態を知り、必要な対策を講じることが大切です。
『認知症と向き合う365』は、認知機能チェックやMRI画像のAI解析により、脳の変化を可視化できる認知症対策サービスです。専門家への相談も可能で、不安を感じたときに頼れる選択肢となります。脳の健康を守る第一歩としてぜひご検討ください。
今から脳の健康に取り組むことが、将来のいきいきとした暮らしにつながります。まずは無理なく始められるところから始めてみましょう。
- 画像素材:PIXTA
【参考文献(ウェブサイト)】
- 長寿医療研究センター(n.d.). 良い生活習慣と脳の老化【脳老化予防】. [オンライン]. 2025年8月26日アクセス,
https://www.ncgg.go.jp/ri/advice/53.html - 長寿科学振興財団(2019). 老化とは何か?. [オンライン]. 2025年8月26日アクセス,
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/rouka/rouka.html - 富山大学和漢医薬学総合研究所(2021). 筋肉が認知症発症をコントロールする!~動かさないことで衰えた筋肉から分泌される有害分子を発見~. [オンライン]. 2025年8月26日アクセス,
https://www.inm.u-toyama.ac.jp/result/2021_1025/ - 野田市役所(2023). 筋トレの新たな主役「マイオカイン」(市報のだ3月15日号掲載). 2025年8月26日アクセス,
https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/fukushi/hoken/1017562/1025452.html - 福島県立医科大学(2023). いごころVol.30. [オンライン]. 2025年8月26日アクセス,
https://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/kouhou/vol_30.pdf
【参考文献(電子ジャーナル)】
- 眞鍋康子(2018). マイオカインは運動模倣薬となるか?. YAKUGAKU ZASSHI, 138巻 (2018)10号, 1285-1290.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/yakushi/138/10/138_18-00091-5/_pdf
【参考文献(書籍)】
- 秋下雅弘(2023). 目で見てわかる認知症の予防. 成美堂出版.
- 朝田隆(2025). 軽度認知障害(MCI)がわかる本. 講談社.
- 旭俊臣(2022). 早期発見+早期ケアで怖くない隠れ認知症. 幻冬舎.
- 加藤俊徳(2021). ビジュアル図解 脳のしくみがわかる本. メイツ出版.
- 長尾和宏(2023). コロナと認知症~進行を止めるために今日からできること~. ブックマン.
この記事の監修者

佐藤俊彦 医師
福島県立医科大学卒業。日本医科大学付属第一病院、獨協医科大学病院、鷲谷病院での勤務を経て、1997年に「宇都宮セントラルクリニック」を開院。
最新の医療機器やAIをいち早く取り入れ、「画像診断」によるがんの超早期発見に注力、2003年には、栃木県内初のPET装置を導入し、県内初の会員制のメディカル倶楽部を創設。
新たに 2023年春には東京世田谷でも同様の画像診断センター「セントラルクリニック世田谷」を開院。
著書に『ステージ4でもあきらめない 代謝と栄養でがんに挑む』(幻冬舎)『一生病気にならない 免疫力のスイッチ』(PHP研究所)など多数。



