認知症かもしれないと思った際の相談先と相談内容について解説

年齢を重ねていくなかで、「最近、少し様子が変かもしれない」と感じたことはありませんか。あるいは、「もしかして認知症かもしれない」と、ふと不安を感じた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、そうした小さな違和感のなかに、認知症の初期のサインが隠れていることがあります。初期の認知症は目立った症状が少ないため、「なんとなくおかしいかも?」という感覚を見逃さないことがとても大切です。
また、認知症は、まだまだ誤解や偏見の多い病気です。あらかじめ正しい知識をもっておくことで、万が一「認知症かもしれない」と感じたときに落ち着いて対応できるようになります。
今回は、認知症の基本的な種類や初期症状、そして困ったときに相談できる窓口を紹介していきます。
認知症の種類
「認知症」はある特定の病気である、と考えている方も多いかもしれません。しかし実際には、認知症という名前の特定の病気があるわけではありません。認知症とは、さまざまな原因によって脳の働きが低下し、日常生活や社会生活に支障がでている状態を総称したものです。
認知症の原因となる病気は、100種類以上もあるといわれています。そのなかには、甲状腺機能低下症やビタミン欠乏症など、脳以外の身体の病気やトラブルが原因で起こるケースもあります。こうした身体の不調による認知症は、治療によって回復が期待できることが少なくありません。
一方で、私たちが一般的にイメージする認知症は、アルツハイマー型認知症や血管性認知症といった脳の病変による進行性のタイプです。実際に、認知症と診断された方の9割近くは、こちらに分類されています。
多くの場合、認知症は進行性であり、時間の経過とともに思考力・判断力・言語能力などの認知機能が徐々に低下していき、さらに進行すると身体機能にも影響があらわれることがあります。
ここからは、日本人に多く見られる4つの代表的な認知症のタイプをみていきましょう。
アルツハイマー型認知症
認知症と聞くと、アルツハイマー型認知症を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。実際に認知症と診断された方のうち、最も多いのがこのタイプで、全体の半数以上を占めるとされています。
アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞にアミロイドβなどの老廃物が蓄積し、周辺の神経細胞が徐々に死滅していくことで脳が萎縮し、認知機能の低下を引き起こすといわれています。
特に、早い段階で影響を受けやすいのが「海馬」と呼ばれる部位です。海馬は記憶をつかさどる部位であるため、「さっきのことをすぐに忘れる」「同じ話を何度もする」といった短期記憶の障害が初期から目立つことが多くあります。

画像素材:PIXTA血管性認知症
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血・くも膜下出血などの脳血管障害により、脳の一部が損傷を受けることで引き起こされるタイプの認知症です。
脳血管障害が引き起こされる原因として、高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙などの、いわゆる生活習慣病が大きく関係しています。そのため、生活習慣病のリスクが高まりやすい50代以降から血管性認知症も増加傾向にあります。
血管性認知症の大きな特徴は、「症状のあらわれ方に個人差が大きいこと」です。これは、損傷を受ける脳の部位によって影響される認知機能が異なるためです。
たとえば、言語に関わる部位が障害を受けた場合は、言葉が出にくくなる一方で記憶力には大きな影響がでないこともあります。また、障害を受けていない脳の機能はそのまま保たれるため、「できること」と「できないこと」の差が目立ちやすいのも血管性認知症の特徴です。
レビー小型認知症
レビー小体型認知症は、レビー小体と呼ばれる異常なたんぱく質が脳内に蓄積することにより、脳の働きの低下を引き起こす認知症です。
レビー小体型認知症では、記憶障害よりも先に身体面の変化があらわれることが多いのが特徴です。たとえば、便秘や嗅覚の低下・立ちくらみなど、一見すると認知症とは関係なさそうな症状が初期からみられることがあります。
また、「幻視(実際には存在しないものが見える)」が出現するケースも多く、目の病気と誤解されて眼科を受診する人も少なくありません。レビー小体型認知症は、症状のあらわれ方にばらつきがあり、日によって調子が良いときと悪いときの差が大きいのも特徴です。
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、特に脳の前頭葉と側頭葉に萎縮がみられるタイプの認知症です。前頭葉は「感情や行動の制御」を、側頭葉は「言語の理解や記憶」を担っており、それぞれの機能低下に応じて症状があらわれます。
前頭葉の萎縮が進むと、感情を抑えることが難しくなったり、社会的なルールを無視したりするような行動が増えることがあります。また、側頭葉の機能が低下すると、言葉の意味がわからなくなったり、会話がうまく続けられなくなったりします。
そのため、前頭側頭型認知症では、もの忘れなどの記憶障害よりも先に、「怒りっぽくなった」「反社会的な行動が目立つようになった」といった「人格が変わったようにみえる」変化があらわれることが多いのが特徴です。
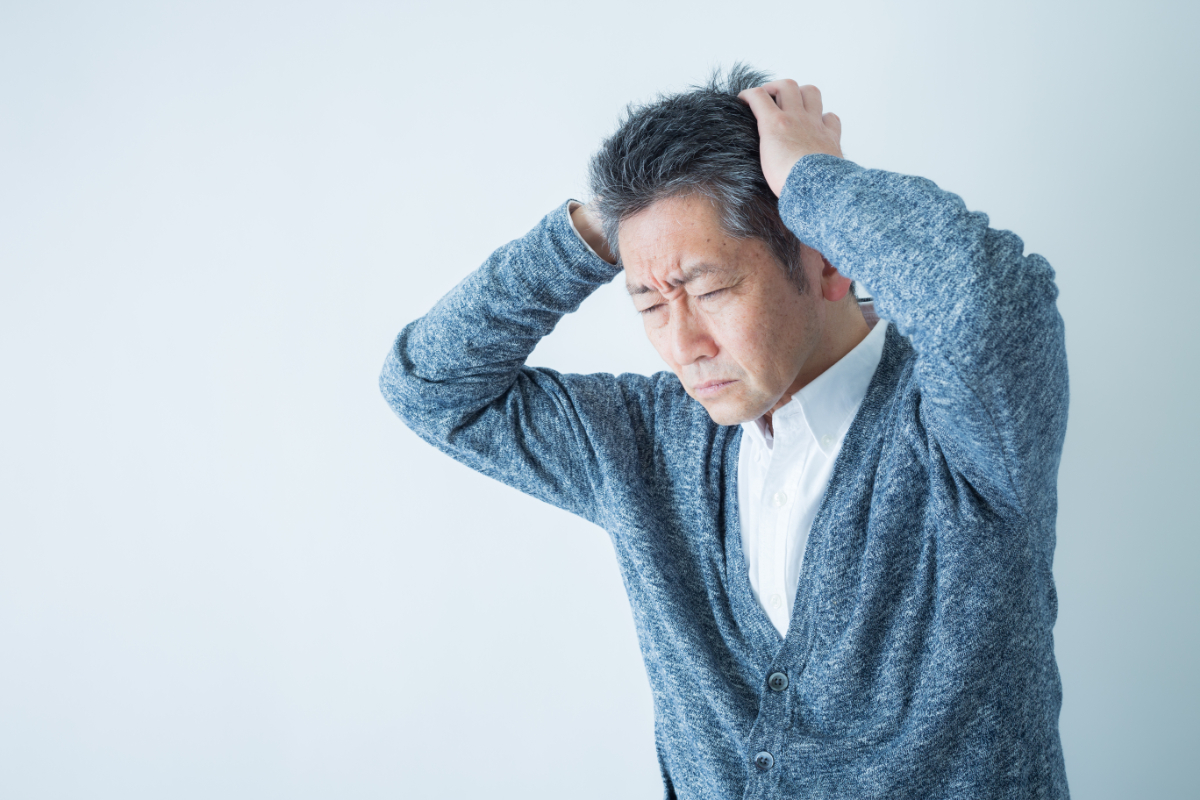
画像素材:PIXTA認知症の初期症状
ここまで、日本人に多く見られる4つの代表的な認知症について紹介してきました。ここからは、どのタイプの認知症にも共通してあらわれやすい初期症状についてみていきましょう。
前提として、どのタイプの認知症であっても、「これがあれば認知症」となるような明確な診断基準はありません。しかし、あえて線引きをするなら、「以前は普通にできていたことが急にできなくなった」「日常生活に支障が出るようになった」などの場合は認知症の可能性が考えられます。
以下のような症状が最近になって目立つようになった、あるいは、以前よりも悪化していると感じるようになったという場合は、医療機関で相談することを検討してみてください。
面倒に感じることが増えた
「なんでも面倒に感じてしまう」「以前のようにやる気が出ない」といった変化を感じていませんか。実は、認知症の最初期には、もの忘れなどの記憶障害よりも先に「意欲の低下」があらわれるといわれています。
脳機能が徐々に低下すると、何気ない日常の作業にも時間やエネルギーが必要になり、それが「面倒くさい」「しんどい」といった感覚につながります。
たとえば、「何をするにも億劫」「料理するのが面倒になってやめた」「長年の趣味が楽しくない」などの変化は、脳の働きに何らかの変化が起きているサインかもしれません。
もの忘れが多い
年齢を重ねるにしたがってもの忘れが増えるのは自然なことです。しかし、明らかに記憶力が低下していたり、それによって日常生活に支障がでてきたりする場合には注意が必要です。
たとえば、「人との約束を覚えていない」「今何をしようとしたかすぐ忘れる」「ひんぱんに置き忘れや探し物をしている」といった行動が続く場合は、単なるもの忘れではなく、認知症の初期症状の可能性があります。
理解力・判断力の低下
認知症の初期には、理解力や判断力にも変化がみられることがあります。
たとえば、「ATMでお金を下ろす」「洗濯機を操作する」といった日常の動作には、機械の仕組みを理解し、手順を判断する認知機能が必要です。認知機能が低下すると、これらの操作にとまどったり、時間がかかったりするようになることがあります。
「以前は使えていた家電が使えなくなった」「操作に前よりも時間がかかる」といった場合は、脳の働きに変化が起きているサインかもしれません。
感情がコントロールできない
感情のコントロールも、非常に高度な脳の働きによって支えられています。そのため、認知症の初期には、「怒りっぽくなる」「感情の起伏が激しくなる」といった変化がみられることがあります。
たとえば、「以前は穏やかだったのに些細なことで怒るようになった」「疑い深くなって身近な人に攻撃的な態度をとるようになった」といった場合は、性格の変化としてあらわれた認知症のサインかもしれません。
認知症が疑われる際の相談先
「もしかして認知症かも」と不安に感じたとき、どこに相談すればいいのか悩む方も多いのではないでしょうか。
現時点では、認知症を完治させる治療法は確立されていません。しかし、できるだけ早い段階で気づき専門的な支援につなげることで、進行を遅らせたり、自分らしい生活をより長く続けたりできる可能性があります。
ここでは、困ったときに頼れる主な相談先を4つご紹介します。

画像素材:PIXTA相談先①かかりつけ医
普段から受診しているかかりつけ医がいる場合は、まずはその医師に相談するのがおすすめです。かかりつけ医であれば日ごろの状態をよく把握しており、わずかな変化にも気づきやすいため、認知症の初期サインにも早く対応できる可能性も高いでしょう。
必要に応じて、認知症の専門医療機関や専門医への紹介状を発行してもらえるため、スムーズに次のステップへ進むことができます。
相談先②もの忘れ外来
もの忘れ外来は、認知症やその前段階である軽度認知障害(MCI)の早期発見と進行予防を目的とした専門外来です。専門医による問診、心理検査(認知機能検査)、脳の画像診断などを通じて、認知機能の状態を詳しく調べてもらうことができます。
全国の多くの医療機関で受診でき、かかりつけ医がいない方でも利用しやすいのがおすすめのポイントです。また、検査結果に応じて治療方針や支援サービスの提案も受けられるため、「とにかく早めに専門的な診断を受けたい」という方に向いています。
相談先③地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者やそのご家族の生活を総合的に支えるために設置された地域の相談窓口です。保健師や社会福祉士などの専門スタッフが常駐しており、認知症に関する不安や介護の悩みを気軽に相談できます。
実際に検査をおこなう施設ではありませんが、「まず何から始めればいいか分からない」というときでも頼れるのが大きなメリットです。相談は無料で、必要に応じて認知症疾患医療センターなどの専門機関への案内も受けられます。地域包括支援センターは、中学校区を目安に全国に設置されているため、ご近所にもないか一度確認してみましょう。
相談先④認知症疾患医療センター
認知症疾患医療センターは、専門的な診断や支援を提供するために整備された、認知症に特化した医療機関です。国の補助を受けて、自治体が指定した医療機関(総合病院・精神科病院・大学病院など)が運営を担っています。
センターには、精神科医・臨床心理士・認知症看護認定看護師といった専門スタッフが在籍し、認知症に関する幅広い相談に対応しています。必要に応じて、より適切な医療機関の紹介や生活支援の提案を受けることも可能です。
認知症疾患医療センターは、全国に500か所以上設置されており(令和6年12月時点)、地域包括支援センターなどを通じて案内されることが一般的です。

画像素材:PIXTA認知症が疑われる際に相談するべき内容
認知症が心配になり医療機関に相談する際、いざとなるとうまく説明できなかったり、何を伝えればよいか分からなかったりすることがあります。そこで、事前に相談内容を整理しておくことをおすすめします。
ここでは、相談時に伝えるべきポイントについて、詳しくご紹介します。
気になる症状の具体例
まずは、本人が感じている気になる症状や変化について、できるだけ具体的にメモしておくことが大切です。特に、「いつ・どこで・どんなふうに」困ったのかを記録しておくと、後から振り返りやすく、医療者にとっても重要な判断材料になります。
たとえば、
- 同窓会の会場までの道順がわからず遅刻した
- 書類を書く際に、簡単な漢字が思い出せなかった
- 病院からの帰り道で迷った
こうした出来事に加えて、「最近眠れない」「胃腸の調子が悪い」など、一見認知症と関係なさそうな体調の変化も含めて記録しておくとよいでしょう。
家族や周囲の人から見た変化
本人が気づきにくい変化は、家族や身近な人が感じた違和感から明らかになることがあります。そのため、周囲の人が「なんだか様子がおかしい」と感じた小さな変化を日常的に記録しておくと、普段の状態をより正確に知る手がかりになります。
たとえば、
- 会話中に発言が少なくなった
- 何度も同じ質問をするようになった
- 日中ぼんやり過ごす時間が増えた
- ちょっとしたことで怒りっぽくなった
このような記録は、本人が伝えきれない状態や感覚を補ってくれるため、医師の判断や診断に役立ちます。
認知症の相談に関するよくある質問
認知症相談はネットでもできますか?
近年、一部の医療機関や専門サービスにおいては、オンライン相談にも対応しています。自宅から相談できるため、外出が難しい方や、人目が気になる方にとっては利用しやすい選択肢となるでしょう。
ただし、これらのオンライン相談は診断や治療行為を目的とするものではなく、健康保険の適用外であることが多いため、費用がやや高めになる傾向があります。気になる症状がある場合には、内容や対応範囲を確認したうえで、自分の状況に合ったサービスを選ぶようにしましょう。

画像素材:PIXTA認知症の相談は無料ですか?
公的な相談窓口である地域包括支援センターや認知症疾患医療センターでは、基本的に無料で相談を受け付けています。費用面で不安があり、いきなり医療機関に行くのはためらわれる場合は、まずこうした公的機関を活用するのがおすすめです。
また、必要に応じて、介護サービスや医療機関への案内、支援制度の紹介なども受けられるため、「どこから手をつければいいか分からない」というときの第一歩としても有効です。
まとめ
今回の記事では、認知症の種類や初期症状、相談先や相談時のポイントについて紹介してきました。認知症は誰にでも起こりうる可能性のある病気だからこそ、「まだ大丈夫」と思える今のうちから備えておくことが何より大切です。
認知機能の変化は、本人も周囲も気づきにくいことがあります。だからこそ、日常的に脳の状態を把握する仕組みがあると安心です。
そのようなときに役立つのが、認知症対策のオールインワンサービス『認知症と向き合う365』です。『認知症と向き合う365』では、オンラインや電話で受けられる認知機能チェックに加え、AIがMRI画像を解析して海馬の容量や脳の状態を詳しく調べる「BrainSuiteⓇ」など、日々の変化を見逃さないためのサービスを揃えています。
相談先を知り、症状に気づき、そして未来の自分のために今から行動を起こすこと。『認知症と向き合う365』は、それらを支えるパートナーとして、あなたの備えを後押しします。
早めの準備が未来の安心につながります。将来の不安を減らし、よりよく生きるために。今できる一歩から始めてみませんか。
- 画像素材:PIXTA
【参考文献(ウェブサイト)】
- 厚生労働省(2024). 認知症疾患医療センター運営事業. [オンライン]. 2025年8月15日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/content/001407400.pdf - 厚生労働省(n.d.). 認知症に関する相談先. [オンライン]. 2025年8月15日アクセス,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00003.html
- 厚生労働省(n.d.). 主な認知症施策. [オンライン]. 2025年8月15日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html - 国立長寿医療研究センター(2024). あたまとからだを元気にするMCIハンドブック. [オンライン]. 2025年8月15日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/content/001272358.pdf - 東京都健康長寿医療センター(n.d.). 認知症疾患医療センター [オンライン]. 2025年8月15日アクセス,
https://www.tmghig.jp/hospital/department/dementia-center/dementia-center/medical-center-for-dementia/
【参考文献(書籍)】
- 秋下雅弘(2023). 目で見てわかる認知症の予防. 成美堂出版.
- 朝田隆(2023). 認知症グレーゾーンからUターンした人がやっていること. アスコム.
- 旭俊臣(2022). 早期発見+早期ケアで怖くない隠れ認知症. 幻冬舎.
- 長尾和宏(2023). コロナと認知症~進行を止めるために今日からできること~. ブックマン.
- 山川みやえ・繁信和恵・長瀬亜岐・竹屋泰(2022). 認知症plus若年性認知症. 日本看護協会出版会.
- 若井克子(2022). 東大教授、若年性アルツハイマーになる. 講談社.
- クリスティーン・ボーデン/桧垣陽子(2003). 私は誰になっていくの?――アルツハイマー病者からみた世界. クリエイツかもがわ.
この記事の監修者

佐藤俊彦 医師
福島県立医科大学卒業。日本医科大学付属第一病院、獨協医科大学病院、鷲谷病院での勤務を経て、1997年に「宇都宮セントラルクリニック」を開院。
最新の医療機器やAIをいち早く取り入れ、「画像診断」によるがんの超早期発見に注力、2003年には、栃木県内初のPET装置を導入し、県内初の会員制のメディカル倶楽部を創設。
新たに 2023年春には東京世田谷でも同様の画像診断センター「セントラルクリニック世田谷」を開院。
著書に『ステージ4でもあきらめない 代謝と栄養でがんに挑む』(幻冬舎)『一生病気にならない 免疫力のスイッチ』(PHP研究所)など多数。



