親の認知症予防に役立つ10の方法|今すぐ始められる習慣をご紹介

年齢を重ねた親の様子をみて、「最近もの忘れが増えたかも」「なんだか様子が変わった気がする」と感じることはありませんか。認知症は誰にでも起こりうる身近な病気ですが、早めの予防や対策に取り組むことで、進行を遅らせることが期待できます。親の認知症を予防することは、本人の生活の質(QOL)を守るだけではなく、家族の介護負担を軽減するうえでも大切です。
今回は、親の認知症を予防するために知っておきたいポイントや、日常に取り入れやすい具体的な予防方法・習慣についてわかりやすく紹介していきます。
親の認知症予防が重要な理由
介護が必要になった原因の第3位が、認知症であることをご存じでしょうか。親が高齢になるにつれて、「認知症予防」は決して他人事ではなくなります。将来的な親の介護リスクを少しでも軽減するためにも、日頃の認知症予防は非常に重要です。
認知症は、現時点では完治のための治療方法が確立されていないため、一度発症すると長期にわたるケアやサポートが必要になります。認知症による介護期間は平均して約10年ともいわれ、その間は親本人だけではなく、家族にも大きな負担がかかります。
また、認知症は単に「記憶力が低下する」「もの忘れが増える」といった症状だけではなく、「その人らしさ」や人格そのものに影響を与える病気です。親が認知症になると、家族の関係性や親への印象が大きく変わってしまうこともあり、それが精神的なストレスや家族の絆に悪影響を与えることもあります。
もちろん、認知症にならないことが理想ですが、万が一発症したとしても早期に気づくことができれば、介護体制の準備や必要な情報収集、家族で話し合う時間を確保できます。
つまり、親の認知症予防は単に病気を防ぐだけではなく、親本人の生活の質を守り、家族みんなの未来を守ることにもつながります。大切な親が「その人らしく」過ごせる時間を少しでも長く保つために、できることから取り組みを始めていきましょう。

画像素材:PIXTA認知症になりやすい人の特徴
近年の研究により、認知症にはなりやすい人の特徴(リスク因子)があることが明らかになっています。そして、その多くは普段の生活習慣や健康状態と深い関わりがあります。
たとえば「運動不足」「食生活の乱れ」「喫煙」「社会的な孤立」「難聴の放置」などは、認知症のリスクを高める要因とされています。一見些細に思えるようなことが、実は認知症の引き金になることもあるのです。
海外では、これらの背景から認知症を「生活習慣病のひとつ」と捉える考え方も広まりつつあります。つまり、日常生活で改善できる部分を見直すことで、認知症予防につながる可能性があるということです。
そして、このリスク因子が複数重なることで、さらに認知症の発症リスクを高めるともいわれています。特に、以下の項目に当てはまる場合は、認知症リスクが高い傾向にあるので注意が必要です。
- 耳が聞こえにくい(難聴)
- 糖尿病を患っている
- 慢性的な高血圧
- 肥満気味である
- 食生活が偏っている
- 日常生活で運動の機会が少ない
- 社会的な交流に乏しい
- 長期的に喫煙を続けている
- 歯を複数本失っている
これらにいくつか当てはまる場合は、できるだけ早めに生活習慣を見直して認知症予防に取り組むことをおすすめします。
親の認知症予防が期待できる方法10選
ここまで、「認知症になりやすい人の特徴」とその背景にあるリスク因子について紹介してきました。逆に考えれば、この「リスク因子」を少しずつ減らしていくことが認知症の予防につながります。
しかし、認知症のリスク因子の多くは日常の習慣や健康状態に関係しているため、簡単に改善できるものばかりではありません。特に、高齢の親世代に新しい生活習慣を取り入れてもらうには時間や配慮が必要です。だからこそ、できるだけ早いうちから予防に取り組むことが大切なのです。
また、何より重要なのは、親本人の意思を尊重することです。無理に生活習慣を変えさせようとするのではなく、「一緒に試してみよう」と寄り添うスタンスが前向きな行動につながります。
ここからは、親子で一緒に始めやすく、継続しやすい認知症予防10選を紹介していきます。日々の暮らしのなかに少しずつ取り入れることで、親の健康を守るだけではなく、自分自身の認知症予防にも役立つヒントが見つかるはずです。
親の認知症予防①身体活動を増やす
運動習慣は、認知症予防にとって非常に大切な要素のひとつです。実際に、よく身体を動かす人は認知症になりにくい傾向がある、という研究結果も報告されています。
特におすすめしたいのは、息が少し弾むくらいの軽め運動を週に2~3回、1回あたり30分程度おこなうことです。「おしゃべりしながらの散歩」や「近所の公園を少し早足で歩く」といった気軽な運動でも、十分に効果が期待できます。
また、親がヨガや水泳、ダンスなどに興味を持っている場合は、好きな運動を選ぶのがベストです。運動を義務のように感じてしまうとかえってストレスになってしまうこともあるため、あくまで楽しく、気持ちよく続けられることが重要です。
ただし、運動する際には転倒やケガに注意が必要です。親が安全に、そして前向きに身体を動かせるよう、無理のない範囲でサポートしましょう。
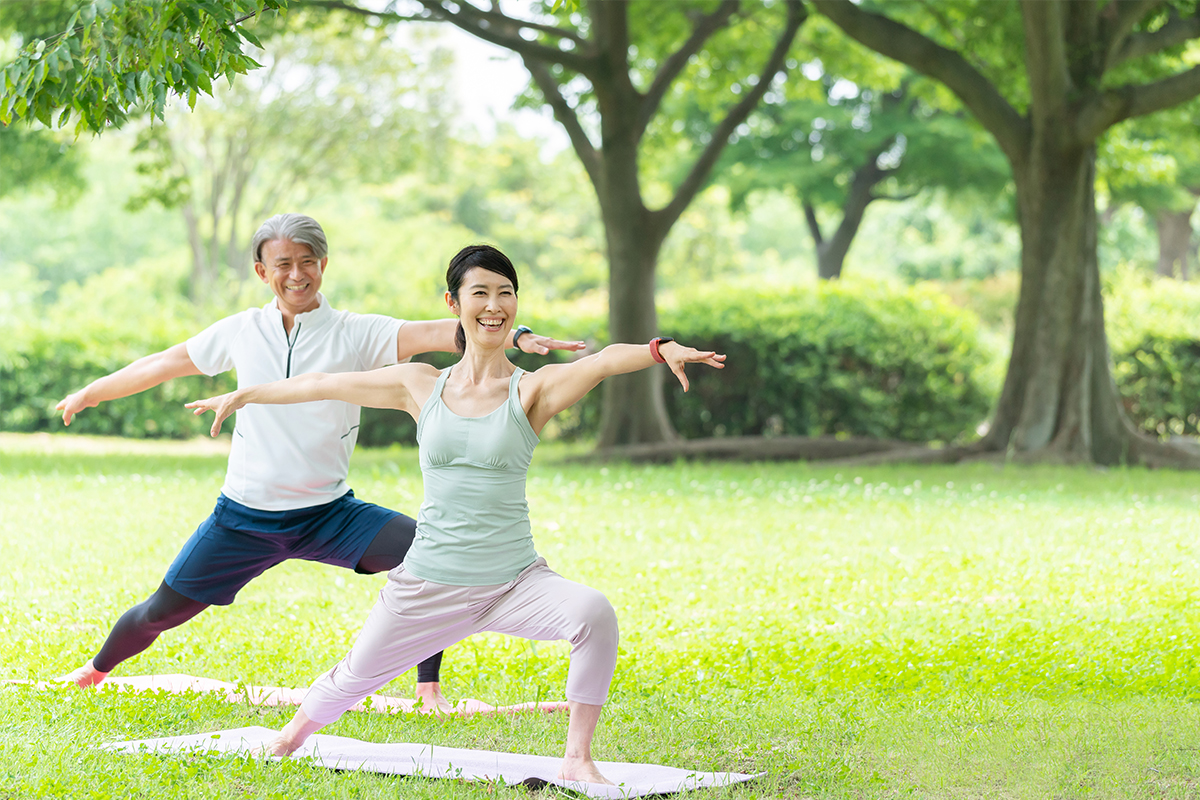
画像素材:PIXTA親の認知症予防②転倒に注意する
認知症の予防というと脳機能や記憶力ばかりに注目しがちですが、実は「転倒によるケガ」も認知症リスクを高める重大な要因になることがあります。
介護が必要になった原因の第1位は、転倒や骨折による運動機能の障害です。高齢になるほど、ちょっとした転倒が寝たきりや外出の減少につながり、結果として認知症のリスクを高めてしまうことが少なくありません。
年齢とともに筋力や関節の柔軟性が衰えるのは自然なことですが、だからこそ日常生活での「転ばない工夫」を積極的に取り入れることが大切です。
具体的には、以下のような方法が効果的です。
- 室内の段差をなくし、滑りやすい場所にはマットを敷く
- 夜間のトイレに備えて足元灯を設置する
- 屋内用の滑りにくい靴や靴下を選ぶ
- 転倒防止のための筋力トレーニングやストレッチを日課にする
転倒を予防することは、身体の健康を守るだけではなく、親の脳や認知機能の健康を守ることにもつながります。「ケガをしない暮らし」を意識することは、高齢期の認知症予防の基礎であるともいえます。
親の認知症予防③食生活を見直す
身体の健康と同じように、脳の健康も毎日の食事によって支えられています。偏った食生活は、認知症の発症リスクを高めることが分かっており、食事内容を見直すことも認知症予防にとって非常に重要なポイントです。
特に近年注目されているのが、「地中海食」と呼ばれる食事スタイルです。地中海食とは、イタリアやギリシャなどの地中海沿岸地域に根づく食文化で、オリーブオイルをおもな脂質源にし、野菜・果物・魚・豆類・ナッツなどを積極的に摂るバランスの良い食事法です。こうした食生活を日常に取り入れることで、認知症リスクの軽減が期待できるとされています。
まずは以下のようなポイントから、親が無理なく取り組める範囲で毎日の食事に取り入れてみましょう。
- 野菜や果物を毎日の食事に多めに取り入れる
- 魚を意識して食べるようにする(週2回以上がおすすめ)
- 肉を豆類やナッツなど植物性タンパク質に置き換える
- バターの代わりにオリーブオイルを使う
完璧を目指す必要はありません。親のペースに合わせて、少しずつ「脳にやさしい食事」を取り入れていくことが大切です。
親の認知症予防④禁煙する&飲酒を控える
喫煙や過度な飲酒は、健康全般に悪影響を及ぼすだけではなく、認知症のリスクを高める要因にもなります。特に喫煙は、血管にダメージを与えて脳の働きにも影響することがわかっており、予防の観点からは禁煙が推奨されています。
いちばん避けたいのは「これまで通り吸い続けること」です。しかし、喫煙がストレス解消の手段になっている方も多いため、無理に一気にやめようとするのではなく、本数を徐々に減らすことからでも構いません。できる範囲で取り組むことが、長く続けていくためにもおすすめです。
また、飲酒も認知症と関係があるとされています。健康のためにアルコールは適量を守ることが大切です。親が毎日飲酒しているような場合は、「休肝日を設ける」「量を決める」といった形で見直しを提案してみるのもよいでしょう。
禁煙や飲酒量の調整には思わぬメリットもあります。節約できたお金を趣味や旅行に使えるようになれば、生活に楽しみが増え、それ自体が脳への良い刺激となります。これは、認知症予防にもつながる前向きな変化です。
無理にやめさせようとするのではなく、親の気持ちに寄り添い、できることから一緒に取り組んでいきましょう。

画像素材:PIXTA親の認知症予防⑤視力の低下を見過ごさない
意外に思われるかもしれませんが、視力の低下を放置することも認知症のリスクを高める要因のひとつとされています。見えづらい状態が続くと、新聞や本を読むことをやめてしまったり、外出を控えるようになったりと、生活の幅が自然と狭くなってしまいます。こうした変化が、脳への刺激や交友関係の減少につながり、認知症のリスクを高めることがあります。
「新聞が読みづらい」「テレビの文字が見えにくい」など、視力の変化に気づいたら、できるだけ早めに眼科を受診することをおすすめします。高齢になると、白内障や緑内障といった目の病気が進行している場合もあるため、定期的なチェックが大切です。
また、必要に応じて眼鏡を見直したり新調したりするだけで、視界がはっきりして気持ちが前向きになることも多くあります。「よく見える」ことは、生活の質を守るうえでも欠かすことができません。小さな変化を見逃さず、親の視力にも気を配りましょう。
親の認知症予防⑥聴力の低下を放置しない
加齢による聴力の低下も、認知症のリスク要因のひとつであることがわかっています。聴力は少しずつ落ちていくため、本人がその変化に気づきにくいことも少なくありません。だからこそ、家族が変化に気づいてあげることが大切です。
「最近、会話のなかで聞き返すことが増えた」「テレビの音量が以前より大きい」など、ふとした違和感があれば、さりげなく声をかけてみましょう。聴力の低下を放っておくと、人との会話や外出を避けがちになり、結果として社会的な孤立や脳への刺激の減少を招くことがあります。
まずは一度、耳鼻科で聴力検査を受けてみることをおすすめします。意外にも、「耳あかのつまり」が原因で聞こえにくくなっているケースも多く、これは専門医でなければ判断が難しいものです。耳の状態をきちんとみてもらうだけでも安心につながります。
もし問題が見つからなければ、それはそれで安心材料になります。「もう何年も耳の検査を受けていないな」という場合は、この機会に耳の健康もチェックしてみてください。家族の気づきが、親の認知症予防につながる大切なきっかけになります。
親の認知症予防⑦歯のケアをていねいにおこなう
近年の研究では、歯の本数が少ない人ほど認知症のリスクが高まる傾向にあることがわかってきています。特に高齢になると、歯周病が進行して歯を失ってしまう方も少なくありません。歯周病は自覚症状が出にくく、知らないうちに進んでしまうため早めの対応が大切です。
親の認知症予防を考えるうえで、日頃の歯のケアを見直すことはとても大切です。まずは、歯科医院で定期検診を受けてもらい、歯や歯茎の状態をチェックしましょう。必要があれば早めに治療を受けることで、リスクを減らすことにつながります。
また、日々のケアもとても大切です。毎食後の歯磨きに加えて、細菌が増えやすい「起床後」や「就寝前」にもていねいに歯磨きをおこないましょう。さらに、デンタルフロスや歯間ブラシを使うことで、歯と歯の間や歯茎まわりの清掃効果が高まり歯周病のリスクをぐっと減らすことができます。
最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、一度習慣になれば自然と続けられるようになります。親の口腔ケアをサポートすることは、将来の認知症予防だけではなく、会話や食事の楽しみを保つことにもつながります。

画像素材:PIXTA親の認知症予防⑧ストレスを抱え込まないようにする
年齢を重ねるにつれて、ストレスを抱えたときにうまく発散する力が若いころよりも弱くなる傾向があります。身体を動かす機会が減ったり、仕事を退職して人との関わりが少なくなったりすると、生活にメリハリがなくなり気づかないうちにストレスがたまりやすくなります。
親のちょっとした変化に気づいたときは、「最近疲れていない?」「何か気になることある?」など、やさしく声をかけてみましょう。周囲との会話や軽い運動、自然に触れる時間などは、気分転換やストレス緩和に効果的です。
また、人との接点が減ることで「他人の目」を意識することが少なくなり、セルフケアもおろそかになりがちです。だからこそ、意識して日常の中でリフレッシュできる時間をもつことが、心と脳の健康を守るうえでも重要なポイントになります。
ストレスを完全になくすことは難しくても、うまくつき合うことは可能です。親がリラックスできる時間や環境を一緒に考えていくことが、認知症予防にもつながります。
親の認知症予防⑨社会とのつながりを大切にする
年齢を重ねると、仕事を退職したり、子どもが独立したりして、社会との接点が少しずつ減っていくものです。しかし、孤独や社会的な孤立は、認知症のリスクを高める要因のひとつとされています。そのため、親が誰かと関わる機会をもち続けることは、予防の面でも非常に大切です。
しかし、高齢の親にとって、新しい人間関係やコミュニティに飛び込むのは簡単なことではありません。だからこそ、「こんな教室があるみたいだよ」「一緒に見に行ってみようか?」など、さりげなくきっかけをつくってあげると効果的です。
たとえば、地域の体操教室や趣味のサークル、ボランティア活動など、人とのつながりが生まれる場は身近なところにあります。親が関心をもちそうなものがあれば、情報を伝えてみたり、初回だけ付き添ったりすることで不安のハードルを下げることができます。
社会とのつながりをもち続けることは、認知症の予防だけではなく、気分の安定や生活への意欲にも良い影響を与えます。親が「また誰かと話したいな」「次も行ってみたいな」と思えるような環境づくりを、家族でサポートしていきましょう。
親の認知症予防⑩創作的な活動や趣味を大切にする
歌を歌う、楽器を演奏するといった音楽活動や、絵を描く、彫刻を彫るなどの芸術活動は、脳への良い刺激になるうえ、気持ちを前向きに保つためにも効果的だとされています。
こうした創作的な活動は、身体的な負担が少なく、高齢の親でも取り組みやすいです。また、新しいコミュニケーションのきっかけになることもあります。子育てや仕事に追われるなかで遠ざかってしまった昔の趣味などを再開するのも、気持ちが前向きになり脳に良い影響を与えてくれます。
家族としてできるのは、「こんなの好きだったよね」「これ、もう一回やってみない?」とそっと背中を押すことです。必要があれば道具をそろえたり、初回だけ一緒に参加してみたりするのもよいでしょう。楽しみながら続けられる活動を持つことは、親の心と脳の健康を保ち、これからの人生をいきいきと過ごすための大きな支えになります。

画像素材:PIXTA親の認知症を疑ったらおこなうべきこと
「最近、なんとなく様子が変わった気がする」「同じ話を繰り返すことが増えた気がする」など、小さな違和感を覚えたときは放置せずに行動することが大切です。実際、認知症の兆候がでていながら、「まだ大丈夫」と様子を見ているうちに症状が進行し、受診時にはすでにかなり進んでいたというケースも少なくありません。
認知症は、早期発見と早期対応が何より重要です。初期の段階であれば、進行を緩やかにする治療やケアの選択肢も広がり、将来への準備や家族との話し合いの時間も確保しやすくなります。
違和感に気づいたそのときこそ、最初の一歩を踏み出すチャンスです。「気のせいかもしれない」ではなく「念のため確認してみよう」という気持ちで、まずはかかりつけ医や認知症専門の医療機関に相談してみましょう。
かかりつけ医へ相談する
親の様子が気になったときは、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。日頃の体調を把握している医師であれば、小さな変化にも気づきやすく、必要に応じて「もの忘れ外来」などの専門外来への紹介もスムーズにおこなってくれるでしょう。
体調不良やストレスなど、認知症以外の原因による一時的な症状の可能性もあるため、自己判断せず、専門的な視点からアドバイスを受けることで、安心にもつながります。
地域包括支援センターへ相談する
認知症に関する悩みや不安があるけれどまだ診断を受けていない、といった段階でも気軽に相談できるのが地域包括支援センターです。高齢者とその家族のための地域の相談窓口で、医療機関の紹介や介護・福祉サービスの案内なども受けられます。
「病院に行くべきか迷っている」「身近に頼れる人がいない」といったときでも、専門のスタッフが親身に話を聞き、今の状況に応じたサポートを提案してくれます。ひとりで抱え込まず、まずは相談してみることが大切です。

画像素材:PIXTA認知症と向き合う365を利用する
「まだ認知症じゃないと思うけれど、これからがちょっと心配…」と感じている場合には、無理なく始められる対策として、『認知症と向き合う365』をおすすめしてみてはいかがでしょうか。このサービスは、認知症の早期発見をサポートするための検査や、専門スタッフに直接相談できるフォローアップがセットになった、認知症対策のオールインワンサービスです。
スマホや電話で気軽に受けられる認知機能セルフチェックと、全国の提携医療機関で受診できるMRI画像検査がセットになっているので、『認知症と向き合う365』ひとつで、複数の検査を受診できるのが魅力です。
さらに、楽しみながら続けられるよう、オリジナルの落語動画などのコンテンツも随時更新されています。「認知症対策を始めてみようかな」と思ったときに、手軽に始められる選択肢のひとつとして、ぜひ検討してみてください。
まとめ
今回は、親の認知症予防をテーマに、日常生活のなかで実践できる方法を紹介してきました。
親の認知症予防は、将来の介護リスクを減らし、本人と家族の生活の質を守るために非常に重要です。認知症は完治のための治療法が確立されていない病気だからこそ、早めの備えが欠かせません。
生活習慣を見直したり、定期的な健康チェックをおこなうことで、発症リスクを減らしたり、進行をゆるやかにしたりすることに期待できます。身体を動かすことやバランスの良い食生活、視力や聴力のケア、ストレス対策、社会とのつながりをもつことなど、できることから少しずつ取り入れていくことが大切です。
そして、気になる変化があれば、早めにかかりつけ医や専門機関に相談し、適切なサポートを受けることも忘れないでください。親の認知症予防は、家族みんなで支え合いながら取り組んでいくことが大切です。日々の小さな積み重ねが、明るく安心できる未来へつながっていきます。
- 画像素材:PIXTA
【参考文献(ウェブサイト)】
- 厚生労働省(n.d.). 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況. [オンライン]. 2025年7月25日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html - 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(2024). あたまとからだを元気にするMCIハンドブック. [オンライン]. 2025年7月25日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/content/001100282.pdf - テキスト
【参考文献(書籍)】
- 秋下雅弘(2023). 目で見てわかる認知症の予防. 成美堂出版.
- 朝田隆(2017). まだ間に合う!今すぐ始める認知症予防. 講談社.
- 朝田隆(2023). 認知症グレーゾーンからUターンした人がやっていること. アスコム.
- 朝田隆・森進(2023). 認知症を止める「脳ドック」を活かした対策. 三笠書房.
- 森勇磨(2023). 認知症は予防が9割 ボケない7つの習慣. マガジンハウス.
この記事の監修者

佐藤俊彦 医師
福島県立医科大学卒業。日本医科大学付属第一病院、獨協医科大学病院、鷲谷病院での勤務を経て、1997年に「宇都宮セントラルクリニック」を開院。
最新の医療機器やAIをいち早く取り入れ、「画像診断」によるがんの超早期発見に注力、2003年には、栃木県内初のPET装置を導入し、県内初の会員制のメディカル倶楽部を創設。
新たに 2023年春には東京世田谷でも同様の画像診断センター「セントラルクリニック世田谷」を開院。
著書に『ステージ4でもあきらめない 代謝と栄養でがんに挑む』(幻冬舎)『一生病気にならない 免疫力のスイッチ』(PHP研究所)など多数。



