脳ドックで認知症はわかる?早期発見のためにできることを解説
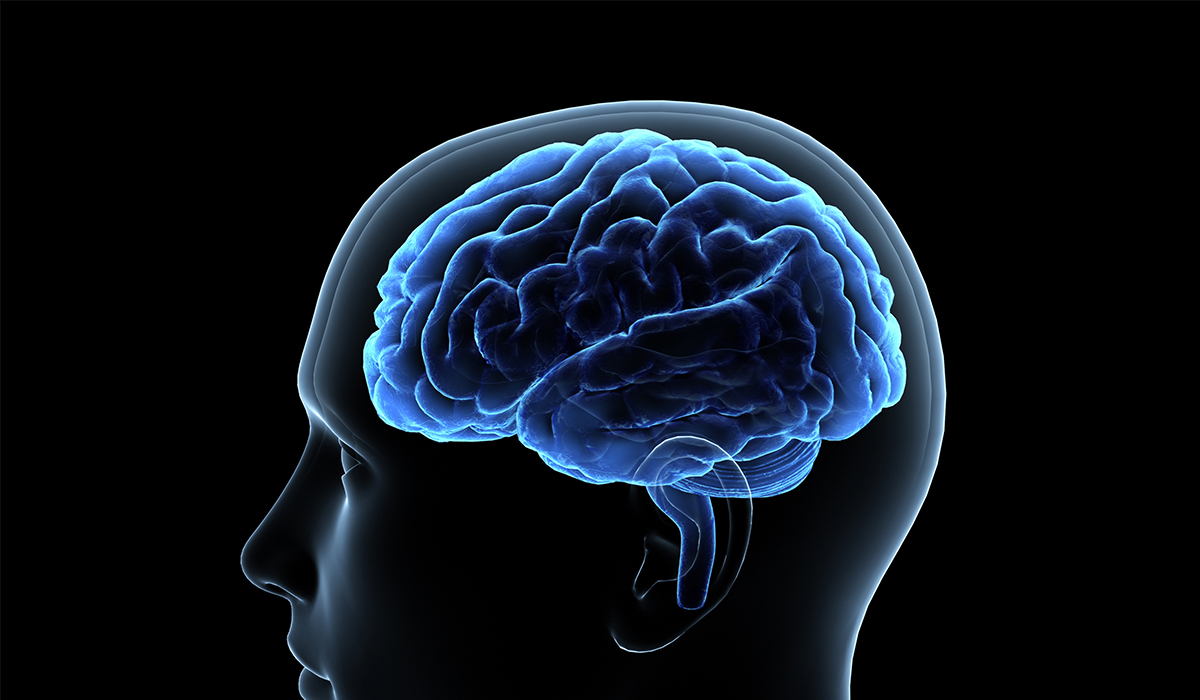
目次 [閉じる]
私たちの脳は、記憶力や判断力・思考力などの「認知機能」だけではなく、呼吸や心拍、体温調整などの「身体機能」までコントロールしている、まさに人体の司令塔と言える重要な器官です。
しかしながら、日頃から脳の健康状態を意識している人はあまり多くありません。一般的な健康診断には脳の詳細な検査は含まれていないことがほとんどで「自分の脳が今どんな状態なのか」は分かりにくいのが現状です。
ですが、近年では医療技術の進展により、MRIをはじめとする脳画像検査が大きく進化しています。脳画像検査を通じて現在の脳の状態をチェックできるだけではなく、脳梗塞や認知症など、重大な脳疾患のリスクを早期に発見することも可能になってきました。
このような背景から注目されているのが「脳ドック」です。「今はまだ元気だけど将来が心配」「認知症に早めに気づいて対処したい」、そうした思いから脳ドックの受診を検討する方も増えてきています。
今回の記事では、脳ドックの基本的な情報について解説するとともに、認知症の早期発見のためにできることを紹介していきます。
脳ドックとは?
脳ドックとは、脳卒中や脳梗塞・くも膜下出血など、自覚症状が出にくい脳の疾患を早期に発見することを目的とした検査です。これらの疾患は、症状が現れてからでは治療や回復が難しいケースが少なくないため、予防的な検査として脳ドックが注目されています。
脳ドックでは、主にMRIやMRAといった画像診断を用いることにより、脳の状態や血管の異常を詳しく確認します。
- MRI検査(磁気共鳴画像)
脳の断面構造を画像化する検査で、脳腫瘍や脳梗塞の有無を確認することができます。 - MRA検査(磁気共鳴血管画像)
脳内の血管の状態を映し出す検査で、動脈瘤や血管の狭窄(狭くなっている状態)や閉塞などの有無をチェックします。
医療機関によっては、これらに加えて頚動脈エコーや血液検査を含むコースが用意されている場合もあります。たとえば、頚動脈エコーでは、首の血管に生じた動脈硬化の状態を確認できるため、より広範なリスク評価につながります。
なお、脳ドックの費用は検査内容やコースによって異なり、一般的な健康診断と比べるとやや高額になる傾向があります。特定の症状や疾患に心当たりがあるときには、脳ドックではなく、専門外来での診察や他の適切な検査を検討することも重要です。
脳ドックの検査で分かること
脳ドックは、現在の脳の状態を画像で確認し、脳の異常の兆候を早期に見つけることを目的とした検査です。そのため、特定の疾患を診断するための検査ではなく、将来的なリスクを幅広くチェックする予防的な意味合いが強いことが特徴です。
MRIやMRAなどの画像検査は、脳内に明らかな異常がないかを調べるだけではありません。「脳血管が細くなっている」「過去に無症候の脳梗塞があった可能性がある」など、現在症状はなくても今後注意が必要なサインも発見することができます。
特に注意が必要なのは、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病を抱えている方です。これらの疾患は脳の血管に負担をかけるため、脳卒中や認知症のリスクが高まることがわかっています。
脳ドックで脳の状態をチェックしておくことは、こうした重大な疾患の予防につながります。ここからは、脳ドックによって発見されやすい脳の疾患やリスクについて、具体的に紹介していきます。

画像素材:PIXTA脳微小出血
脳微小出血とは、脳内の細い血管が破れ、ごくわずかに出血を起こしている状態を指します。出血した血液は「血腫」という塊になり、周囲の脳組織を圧迫することで少しずつ脳にダメージを与えるおそれがあります。これが進行すると、脳内出血や、場合によっては脳梗塞などの重大な疾患を引き起こす可能性があります。
こうした脳微小出血は、非常に小さな変化であるため自覚症状がほとんどなく、気づかないまま進行してしまうことも少なくありません。しかし、脳ドックを受けることで、症状が出る前の段階から異常を捉えることができます。
この段階で発見できれば、生活習慣の見直しなどの対策を講じることで、将来的な脳出血や脳梗塞などのリスクを下げることができます。特に、高血圧や動脈硬化のリスクがある方は脳微小出血が起こりやすいとされているため、定期的にチェックすることが重要です。
脳梗塞
脳梗塞は、脳の動脈が詰まって血流が途絶えることにより、脳の神経細胞が壊死してしまう疾患です。発症すると、片側の手足の麻痺・言葉のもつれ・意識障害などが現れ、重い後遺症が残る場合や、なかには命に関わるケースも見られます。
こうした脳梗塞ですが、発症前にリスクや兆候が見つかることもあります。脳ドックでは、まだ自覚症状がない段階のごく小さな脳梗塞や、血管の狭窄(狭くなっている状態)などの変化を捉えることができます。
これらの変化を放置してしまうと、ある日突然、大きな脳梗塞を発症し、半身麻痺や言語障害などの深刻な障害につながる恐れがあります。さらに、脳梗塞を何度も繰り返すことで認知機能の低下につながり「脳血管性認知症」を引き起こす可能性もあります。
特に、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病がある方は、脳梗塞のリスクが高いとされています。脳ドックを受診することで発症リスクを早めにキャッチし、予防や生活習慣の改善につなげることが重要です。
脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)
脳動脈瘤とは、脳の血管の一部がこぶのように膨らんだ状態を指します。血管の壁が弱くなり、風船のように膨らんだ部分ができている状態で、多くの場合、自覚症状はありません。
しかし、この脳動脈瘤が破裂すると、くも膜下出血という命に関わる重篤な脳血管疾患を引き起こすおそれがあります。くも膜下出血では、突然の激しい頭痛や意識障害・嘔吐などの症状が現れ、早期に処置しないと致命的になるケースもあります。
ただし、脳動脈瘤が見つかったからといって、すべてが破裂するわけではありません。多くの場合は無症状のまま経過観察となりますが、破裂するかどうかを事前に見極めることは非常に難しいため、早めに発見しておくことが望ましいとされています。
脳ドックでは、動脈瘤の有無や大きさ・位置を事前に発見できる可能性があります。将来の重大な疾患を未然に防ぐという意味でも、脳動脈瘤の有無を調べることは非常に有意義です。
脳腫瘍
脳腫瘍とは、頭蓋内(頭のなか)に発生する腫瘍(できもの)の総称です。脳そのものや脳を包む膜・神経などで発生し、発生部位や性質によってさまざまなタイプに分類されます。脳腫瘍は「良性腫瘍」と「悪性腫瘍」に分けられますが、良性であっても注意が必要です。なぜなら、脳は頭蓋骨という限られた空間に収まっているため、腫瘍ができるとその大きさにかかわらず、脳を圧迫してしまうおそれがあるからです。
圧迫によって脳内の圧力が高まると、頭痛・吐き気・視覚障害・言語障害など、さまざまな症状が現れることがあります。また、腫瘍の場所や大きさによっては、命に関わる可能性もあります。
脳ドックでは、脳腫瘍の有無や位置・大きさなどを確認することができます。自覚症状がない段階で発見できれば、経過観察や治療方針の検討につながるため、早期発見の意義が非常に大きい疾患のひとつです。

画像素材:PIXTA脳ドックで認知症のリスクは発見できる?
大前提として、脳ドックは認知症リスクの発見を、主な目的とした検査ではありません。そのため、脳ドックで認知症のリスクを完全に把握できるわけではないということを理解しておく必要があります。ただし、認知症の種類によっては、脳ドックの画像検査でリスクを見つけやすいケースもあります。
たとえば「脳血管性認知症」は、脳梗塞や脳出血などで脳の血管に障害が起こり、その結果、認知機能が低下するタイプの認知症です。脳ドックでのMRIやMRAといった画像検査によって、症状が現れる前の脳の微小な出血や血管の異常を発見できることがあり、それにより脳血管性認知症のリスクの早期発見につながるケースもあります。
一方で、「アルツハイマー型認知症」や「レビー小体型認知症」といった神経変性疾患に分類されるタイプの認知症は、初期段階では脳の画像に明らかな異常が現れにくく、一般的な脳ドックでは見つけることが難しいのが実情です。実際に、脳ドックで異常が見つからなかったにもかかわらず、後に認知症と診断されたケースもあります。
近年では、MRIで撮影した脳の画像をAIなどで解析して脳の萎縮や容量の変化を数値化し、将来的な認知症リスクを捉えることを目指したオプション検査も登場しています。これらのオプションを活用することで、一般的な脳ドックでは見逃されやすい神経変性疾患のリスクに早期に気づける可能性があります。ただし、こうしたオプションはすべての脳ドックに標準で含まれているわけではなく、対応可能な医療機関も限られているため、事前の確認が必要です。
脳ドックと認知症ドックの違い
認知症の可能性をより詳しく調べたい場合には「認知症ドック」という選択肢もあります。脳ドックと認知症ドックはいずれも脳の状態を調べる検査ですが、目的や検査内容に明確な違いがあります。
脳ドックは前述のとおり、脳梗塞や脳出血・脳腫瘍などの脳疾患全般を対象とした、脳の構造的な異常や血管のトラブルを早期に発見することを目的とした検査です。主に、MRIやMRAなどの画像検査によって、現在の脳の健康状態を視覚的に確認することができます。
一方の認知症ドックは、記憶力・判断力・思考力などの認知機能の変化に着目し、認知症のリスクや兆候を早期に見つけることを目的とした検査です。画像検査に加えて、問診・認知機能テスト・血液検査などが組み合わされ、より多角的な評価がおこなわれる点が特徴です。
ただし、認知症ドックを提供している医療機関はまだ限られており、受診できる地域や施設が少ないことに加え、検査費用が比較的高額になることもあります。
また、認知症の検査を希望するときには、必ずしも認知症ドックにこだわる必要はありません。「もの忘れ外来」や「認知症外来」といった専門外来を受診することも有効な選択肢のひとつです。
認知症かどうか判断するために必要な検査
認知症の種類によって、判断のしやすさには違いがあります。また、認知症が引き起こす症状は必ずしもはっきりしているわけではなく「この症状があれば認知症」と断定できる明確な基準がありません。
さらに、認知症で見られる記憶力・判断力・思考力の低下は、加齢による自然な変化や、ストレスや疲労の影響で現れることもあります。そのため、認知症かどうかを正確に判断するには、複数の検査を組み合わせて多面的に評価するのが一般的です。具体的には、医師による問診・神経心理学検査・画像検査・血液検査などが行われます。
ここでは、認知症かどうかを判断するためにおこなわれる代表的な検査を紹介します。
問診
医師が本人や家族から、日常生活の変化やこれまでの体調について詳しく聞き取ります。
「以前はできていたことが最近できなくなった」など、小さな変化を把握することで認知症の兆候をつかむ手がかりになります。

画像素材:PIXTA身体検査
認知機能の低下が、認知症以外の要因によって起こっていないかを調べます。
たとえば、聴力の低下や持病の影響などが原因で「会話が噛み合わない」「もの忘れがひどい」と誤解されることもあります。このような可能性を見逃さないために、身体的な健康状態の確認も重要です。
神経心理学検査
記憶力・注意力・言語能力など、さまざまな認知機能の状態をテスト形式で評価します。
代表的なものには「長谷川式認知症スケール(HDS-R)」や「ミニメンタルステート検査(MMSE)」があり、口頭でのやり取りを通じて客観的に状態を把握することができます。
画像検査
画像検査をする目的は、CTやMRIを用いて脳の構造を確認することにより、認知症と認知症に似た別の疾患(脳腫瘍・正常圧水頭症など)を見分けることです。また、アルツハイマー型認知症などの特定の認知症に見られる特徴的な脳の萎縮がないかを確認する重要な手がかりとなります。
さらに場合によっては、脳の血流や代謝の状態を調べるPETやSPECTといった検査が行われることもあります。
血液検査
血液検査では、ビタミン欠乏や甲状腺機能の異常など、認知機能の低下を引き起こす可能性のある、他の疾患の有無を調べます。現在起きている変化の原因がこれらの疾患である場合、治療によって認知機能が回復することもあるため、血液検査は重要な検査のひとつとされています。
近年では、アルツハイマー型認知症に関する特定の血液バイオマーカー(生体指標)を調べる先進的な検査も一部で実施されています。
認知症リスクを早期発見するためにできること
ここまで、脳ドックや認知症ドック、さらに認知症の診断に用いられるさまざまな検査について紹介してきました。肝心なのは、認知症をできるだけ早く見つけるためには「特定の検査を一度受ければ安心」というわけではない、ということです。
認知症は、早い段階で気づいて適切な対応をとることにより、症状の進行をゆるやかにしたり、認知機能の維持・改善したりする効果に期待ができます。将来の脳の健康を守るためにも、認知症やそのリスクの早期発見は非常に重要です。
では、どうすれば認知症を早く見つけられるのでしょうか。ポイントは、継続的に脳の状態をチェックしていくことにあります。脳の状態は日々少しずつ変化していくため、一度の検査だけで判断するのは非常に難しいとされています。
ここからは、認知症の早期発見に役立つ方法を紹介していきます。ぜひ参考にして、将来の脳の健康に備えてみてください。
脳ドックや認知症ドックを受ける
脳の状態を定期的に確認しておくことは、認知症リスクを早く見つけるうえで非常に大切なポイントです。
一般的な脳ドックでは、脳血管の異常を発見することで脳血管性認知症の兆候をキャッチできる可能性があり、さらにオプションを追加することで、神経変性疾患のリスクにも一定のアプローチが可能です。
また、より詳しく調べたい場合には、認知機能の変化に焦点をあてた認知症ドックの受診も選択肢のひとつです。施設や費用のハードルはありますが、脳の状態を多角的に評価できるというメリットがあります。
目的や関心に応じて適切なコースを受けることが、将来の備えにつながります。
『認知症と向き合う365』を利用する
『認知症と向き合う365』は、認知症リスクの早期発見を目指す方に向けた、認知症対策のオールインワンサービスです。
オンラインや電話で実施できるセルフ認知機能チェックに加えて、AIがMRI画像を詳細に解析する「BrainSuiteⓇ」がセットになっており、脳の状態を数値化してより詳しく把握することができます。この「BrainSuiteⓇ」は、脳ドックのオプションでも使われている注目のサービスです。
さらに、医師や心理士などの専門スタッフに直接相談できるため、セルフ認知機能チェックの結果に不安を感じた方は、認知症予防について気軽に相談できるのも安心なポイントです。
月払い・年払いから選べるサブスクリプション型サービスのため、都度の負担を抑えて続けられることも大きな魅力です。将来の脳の健康に備えて手軽に始められる認知症対策としておすすめです。

画像素材:PIXTAまとめ
今回は、脳ドックの基本的な情報と、認知症の早期発見のためにできることについて紹介してきました。
脳ドックは、脳梗塞や脳出血などの脳疾患に加えて認知症のリスクにも気づける可能性があり、予防的な検査として非常に有効です。ただし、脳ドックだけですべての認知症リスクが把握できるわけではないため、認知症に特化した検査や対策もあわせて検討することが大切です。
将来の健康に不安を感じたときこそ、備えを始めるチャンスです。まずは今できることから脳の健康を守る一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
- 画像素材:PIXTA
【参考文献(ウェブサイト)】
- 一般社団法人日本脳ドック学会(n.d.). 脳ドックとは. [オンライン]. 2025年7月22日アクセス,
https://jbds.jp/brain-dock/index.html
【参考文献(書籍)】
- 秋下雅弘(2023). 目で見てわかる認知症の予防. 成美堂出版.
- 朝田隆・森進(2023). 認知症を止める「脳ドック」を活かした対策. 三笠書房.
- 加藤俊徳(2021). ビジュアル図解 脳のしくみがわかる本 気になる「からだ・感情・行動」とのつながり. メイツユニバーサルコンテンツ.
- 北原逸美(2025). 認知症の教科書. ニュートンプレス.
- 長田乾(2019). ナースが知っておく認知症”これだけ”ガイド. 学研メディカル秀潤社.
- 山田悠史(2025). 認知症になる人 ならない人. 講談社.
この記事の監修者

佐藤俊彦 医師
福島県立医科大学卒業。日本医科大学付属第一病院、獨協医科大学病院、鷲谷病院での勤務を経て、1997年に「宇都宮セントラルクリニック」を開院。
最新の医療機器やAIをいち早く取り入れ、「画像診断」によるがんの超早期発見に注力、2003年には、栃木県内初のPET装置を導入し、県内初の会員制のメディカル倶楽部を創設。
新たに 2023年春には東京世田谷でも同様の画像診断センター「セントラルクリニック世田谷」を開院。
著書に『ステージ4でもあきらめない 代謝と栄養でがんに挑む』(幻冬舎)『一生病気にならない 免疫力のスイッチ』(PHP研究所)など多数。



