アルツハイマー型認知症を予防するためには?

目次 [閉じる]
年齢を重ねるにつれて、認知症について気になってきたという方も多いのではないでしょうか。
認知症とは「脳疾患や脳のトラブルによる認知機能の低下により、日常生活に支障をきたしている状態」を指します。認知症の原因となる病気は複数ありますが、その中で最も多いのが「アルツハイマー病」です。このアルツハイマー病を原因とする「アルツハイマー型認知症」は、現在広く知られている認知症のひとつです。
現代医学では、アルツハイマー型認知症を完治させる治療法や、完全に防ぐ方法は未だ確立されていません。一方で、発症リスクを減らし、予防効果が期待できる方法は複数報告されています。
今回は、アルツハイマー型認知症の特徴や、今日から無理なく実践できる予防のヒントをご紹介します。
アルツハイマー型認知症とは
アルツハイマー型認知症は進行性の脳疾患のひとつで、認知症と診断された方のうち約60〜70%を占めています。
アルツハイマー型認知症では、脳の神経細胞に「アミロイドβ」や「タウたんぱく」といった異常なたんぱく質が過剰に蓄積します。それにより、神経細胞やシナプスにダメージを与え、神経細胞を徐々に死滅させて脳の萎縮を引き起こすと考えられています。
症状が進行するにつれて、ゆるやかに認知機能が低下していき、やがて日常生活に支障をきたすようになります。
アルツハイマー型認知症の症状
症状がゆるやかに進行していくのが、アルツハイマー型認知症の特徴です。
初期段階では、同じ話を何度も繰り返す、今さっきの出来事を思い出せないなど、記憶障害が多く見られるようになります。しかし、それが加齢による「もの忘れ」なのか、脳の病気による症状なのか、区別がつきにくく本人や周囲が見逃してしまうことも少なくありません。
中期になると、記憶障害に加えて見当識障害(時間や場所、人の名前がわからなくなる)や判断力の低下が目立ち始めます。日常生活の中でミスが増える、仕事や家事の段取りがつけられなくなるといった変化が現れ、着替えや入浴といった日常動作にも介助が必要になることがあります。さらに症状が進むと、言葉が出にくくなる、感情表現が乏しくなる、興奮しやすくなる、感情のコントロールが難しくなるなど、認知機能以外にもさまざまな変化が見られることがあります。
後期に至ると、自力での歩行や会話が困難になり、排泄や食事、入浴など生活のすべての場面で介助が必要となるケースが多くなります。こうした状態に至るまでには、平均して数年〜十数年かけて徐々に進行する傾向がありますが、進行速度には個人差があります。
アルツハイマー型認知症の予防のヒント
アルツハイマー型認知症では、後期まで症状が進行すると寝たきりになり、生活のほとんどで他者からの介助を要するケースが少なくありません。
年齢を重ねても、自分らしく自由に過ごしていたい。できれば寝たきりにならず、できることは自分で続けたい、誰しもそう思うのではないでしょうか。
そのために、できるだけ早いうちから「予防」に取り組むことが大切です。残念ながら、現時点ではアルツハイマー型認知症を完全に予防する方法は見つかっていません。しかし、これまでの研究により、アルツハイマー型認知症の発症リスクを高めるさまざまなリスク因子が明らかになっています。このリスク因子をできるだけ減らし、心身の健康を維持することが、アルツハイマー型認知症の予防対策のひとつになります。
ただし、アルツハイマー型認知症のなりやすさには個人差があります。まったく同じ年齢、似たような生活を送っていても、発症する人もいれば、発症しない人もいます。ですが、これは何もアルツハイマー型認知症に限った話ではなく、ほかの多くの病気にも当てはまることです。
だからこそ、自分の将来のために、できるだけ早いうちから予防につながる習慣を取り入れ、リスク因子を減らしていくことが大切です。特別なことをする必要はありません。心と体の健康を意識して、日々の暮らしを少しずつ改善することが、アルツハイマー型認知症の予防につながります。
そして、もうひとつ大事なのは「がんばりすぎないこと」。ストイックに完璧を目指すあまり、逆にストレスが増えてしまっては本末転倒です。自分にとって無理のない範囲で、楽しく続けられる習慣を見つけることが、長い人生を心地よく生きるためのコツとも言えるでしょう。
ここからは、今日から実践できるアルツハイマー型認知症の予防のヒントを紹介していきます。

画像素材:PIXTA規則正しい生活を心がける
アルツハイマー型認知症の予防において、まず意識したいのが「規則正しい生活」を送ることです。
生活リズムの乱れは、糖尿病や高血圧といった生活習慣病のリスクを高める要因になります。これらの病気は、アルツハイマー型認知症の発症リスクを高めることが知られています。
特に、慢性的な睡眠不足や、昼夜逆転のような不規則な生活が続くと、脳の働きにも悪影響を及ぼすとされています。たとえば、記憶力や判断力・集中力の低下を引き起こすだけではなく、認知症に関わる脳内のたんぱく質の代謝にも影響を与える可能性があると言われています。
まずは、以下のような基本的な習慣から見直してみることがおすすめです。
- 毎日決まった時間に起きて、決まった時間に眠る
- 食事をきちんと3食とる(特に朝食を抜かない)
- 夜ふかしや就寝・食事時間のばらつきをなるべく減らす
このようなシンプルな習慣の積み重ねが、体の調子を整えるだけではなく、脳の健康維持にもつながっていきます。
まずは「生活の土台」を整えること。これが、アルツハイマー型認知症の予防の第一歩になります。
脳と体にやさしいバランスのとれた食事を心がける
中国の古い言葉に「医食同源(いしょくどうげん)」というものがあります。これは、食べることは薬を飲むことと同じくらい大切で、健康の基本は毎日の食事にあるという考え方です。もちろん、現代においてもこの考え方は有効で、アルツハイマー型認知症をはじめとする脳疾患の予防においても、食生活は重要な役割を果たすと考えられています。
アルツハイマー型認知症の予防において、特別な食品を摂る必要はありません。大切なのは、カロリーや栄養バランスを意識した「健康的な食事」を心がけることです。まずは、今の自分の食生活を振り返り、改善の余地がないか見つめ直すところから始めてみましょう。スマートフォンのアプリなどを活用すれば、食事内容の記録や栄養バランスのチェックが手軽にできるのでおすすめです。
特に「塩分の摂りすぎ」には注意が必要です。日本人の食生活では味噌や醤油などの調味料を使う機会が多く、知らないうちに塩分を過剰に摂ってしまいがちです。過剰な塩分摂取は高血圧を引き起こし、アルツハイマー型認知症のリスクを高める可能性があるとされています。
最近では、風味を損なわずに塩分を控えられる「減塩味噌」や「減塩しょうゆ」なども販売されており、手軽に減塩に取り組むことができます。無理のない範囲で、少しずつ食生活の改善に取り組んでみてください。
有酸素運動を取り入れる
年齢を重ねると、病気やケガがなくても自然と関節の動きが鈍くなり、筋力も徐々に低下していきます。老齢化による筋肉の変性により「ヘモペキシン」が放出され、脳へのダメージを引き起こし、アルツハイマー型認知症になる可能性を高めることがわかっています。
筋力の維持は、転倒や寝たきりの予防になるだけではなく、筋肉から分泌される「マイオカイン」が脳の活性化を引き起こし、アルツハイマー型認知症の予防にも効果があるとされています。
実際に、運動習慣のある人は、そうでない人に比べてアルツハイマー型認知症のリスクが低かったという研究結果も報告されています。なかでも、ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は、脳の血流を促進し、認知機能の維持に効果的だと考えられています。
なかには「高齢になってから運動を始めるのは大変そう」と感じる方もいらっしゃるでしょう。だからこそ、今から少しずつでも運動習慣を身につけておくことが大切です。
ただし、無理をする必要はありません。まずは、日常に取り入れやすい運動から始めてみましょう。たとえば、
- 毎日の散歩やウォーキングを習慣にする
- 自転車に乗って近所まで出かける
- 若いころに親しんでいたスポーツを再開してみる
- ダンスやヨガなど興味のある新しい活動に挑戦してみる
以上のように、自分のペースで気軽に楽しく続けられるものを選ぶのがポイントです。運動は脳だけではなく、睡眠の改善やストレスの軽減にもポジティブな影響を与えることが知られています。
できることから少しずつ。心地よく体を動かすことが、未来の健康を守る力につながっていきます。
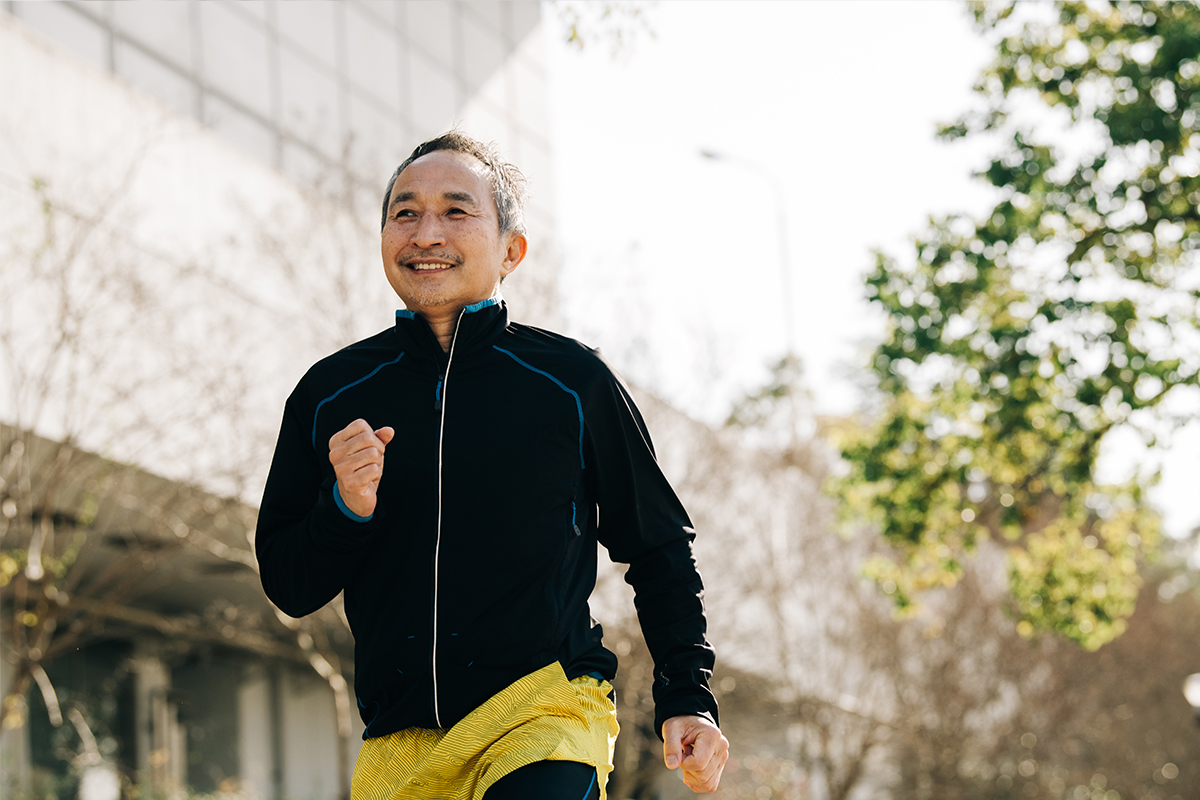
画像素材:PIXTA脳を楽しく使う時間や機会をもつ
筋肉と同じように、脳も使わなければ徐々に衰えていきます。特に、年齢を重ねると使っていない神経回路の働きがどんどん弱まり、認知機能の低下につながることもあります。
とはいえ、毎日同じことばかり繰り返していても脳はやがて慣れてしまい、刺激が薄れてしまいます。大切なのは脳にとって「新しい刺激」を与え続けることです。
いわゆる「脳トレ」にこだわる必要はありません。たとえば、以下のような取り組みも脳を活性化させる良い刺激になります。
- クロスワードパズルやナンプレなど、頭を使う遊びに取り組んでみる
- スマートフォンのゲームアプリに挑戦してみる
- 興味のある新しい趣味を始めてみる
- 普段読まないジャンルの本を読んでみる
- 日常生活エリアから少し離れた知らない場所へ出かけてみる
以上のような「いつもと違うこと」に取り組むだけでも、脳にとっては十分な刺激になります。楽しみながら続けられるものであれば、無理なく習慣化でき、日常生活のなかに自然と取り入れやすくなります。
ポイントは「難しすぎず、飽きずに、楽しく続けられること」です。気軽に始められるものから、自分に合ったものを見つけてみましょう。日々のちょっとした習慣が、将来の脳の健康を支えてくれます。
ストレスや疲労を放置しない
年齢とともにストレスや疲労が蓄積しやすくなり、気づかぬうちに「やる気が出ない」「楽しめない」といった気持ちの変化が生まれることがあります。このような「意欲の低下」は、アルツハイマー型認知症のごく初期に見られる兆候のひとつです。
意外に思われるかもしれませんが、記憶力の低下よりも先に現れることが多いのが、この意欲の低下です。とはいえ、記憶力が加齢とともにある程度自然に衰えていくのに対し、意欲は年齢に関係なく保ち続けることができる力でもあります。
しかし、年齢を重ねて仕事や家庭での責任が増える中で、常に高い意欲を維持するのは簡単なことではありません。だからこそ、ストレスや疲労を溜め込まず、回復のための時間をしっかり確保することが大切です。ストレスを感じたときはしっかり休息をとり、疲労がたまっているときは無理せず回復に努める。そうした日々のセルフケアの積み重ねが、意欲を保ち、長期的な認知機能の維持にもつながります。
「なんとなくやる気が出ない」と感じたとき、それを「年齢のせい」とかたづけず、「心や体が何らかのサインを出しているのでは?」と気づくことが脳の健康を守る第一歩になります。意欲は「健康のバロメーター」でもあります。もし、意欲の低下が長く続くようであれば、その背後にあるストレスや疲労の原因を見直すタイミングかもしれません。自分を見直す時間をしっかりもつことも、未来の脳を守るためには必要です。

画像素材:PIXTAさまざまなことに興味をもち、生きがいを大切にする
アルツハイマー型認知症の予防において大切なのは、運動や食事だけではありません。「好きなことを楽しむ」「いろいろなことに興味をもつ」といった心の豊かさも、脳の健康を守るうえでとても大きな力を発揮します。
趣味や楽しみにしていることがあることで、生活にメリハリが生まれ、生きがいにもつながります。「楽しい」「うれしい」と感じる瞬間は、脳にポジティブな刺激を与えるため、意欲の低下や気分の落ち込みを防ぐうえでも効果的です。
また、新しいことに触れたり、これまでにない体験をしてみたりすることも、脳のさまざまな領域を活性化させるきっかけになります。最初は少し勇気がいるかもしれませんが「なんとなく面白そう」「ちょっと気になる」という気持ちを大切にして、関心の幅を広げていくことが脳への良い刺激につながっていきます。
まずは「やってみよう」という気持ちを大切にしながら、日々の暮らしの中で楽しみや喜びを見つけていくこと。その積み重ねが、アルツハイマー型認知症の予防だけではなく、人生そのものを、よりいきいきとしたものにしてくれるはずです。
手先を動かすことで、脳も心も健やかに
身体の感覚や運動機能を司る脳の領域で、最も大きな割合を占めるのが指先を支配する部位です。つまり、指先を動かすことは脳の広い範囲を活性化させるのです。
たとえば、裁縫や編み物・折り紙・料理・園芸といった手先を使う趣味は、集中力を高めながら脳の働きを促すほか、心を落ち着かせる効果にも期待できます。
認知症予防では、ただ新しいことに挑戦するだけではなく、「刺激」と「リラックス」のバランスをとることも重要です。常に新しい刺激ばかりを追いかけていると、知らないうちに脳や心が疲れてしまうことがあります。そのようなとき、手を動かす穏やかな時間が、脳のリズムを整えるリラックスの時間になります。
忙しい毎日のほっと一息つける時間として「手を動かす時間」を取り入れ、自分のペースで趣味を楽しみ、脳と心の健康をやさしく支えていきましょう。
予防は早いうちから
「まだ若いから、アルツハイマー型認知症なんて関係ない」と考えていないでしょうか。
アルツハイマー型認知症は、一般的には高齢者に多い病気だとされていますが、40〜50代で発症する「若年性アルツハイマー」のケースもあります。病気のメカニズムは高齢者の場合と同様ですが、仕事や家庭などへの影響が大きく、生活に深刻な影響を及ぼすことも少なくありません。
このような背景からも、アルツハイマー型認知症の予防には「早めの対策」が重要です。発症前の段階から生活習慣を見直し、心身の健康を整えておくことで発症リスクを抑える効果に期待できます。特に「最近、なんとなく心身の衰えを感じるようになった…」と感じている30〜40代の方にとっては、まさに今が予防のスタートにふさわしいタイミングかもしれません。
もちろん、アルツハイマー型認知症の予防をはじめるのに遅すぎることはありません。いくつになってからでも、自分のできるところから始めてみることが、将来の健康につながります。年齢にとらわれず、自分自身の将来のために一歩踏み出してみてください。

画像素材:PIXTAアルツハイマー型認知症に関するよくある質問
アルツハイマー型認知症になると脳が萎縮する?
アルツハイマー型認知症では、脳が徐々に萎縮していくのが大きな特徴のひとつです。特に、記憶を司る「海馬」や、思考や判断を担う「大脳皮質」が影響を受けやすく、MRI(磁気共鳴画像)などの画像検査で視覚的に確認できることもあります。
ただし、明確な変化が画像に現れるのは中期以降が多く、初期段階では加齢に伴う自然な変化と区別がつきにくいことも少なくありません。こうした場合には、PET(陽電子放出断層撮影)などの、より精密な検査をおこない、異常たんぱく質の蓄積や脳の代謝の変化を捉えることで、早期診断につながる可能性があります。
アルツハイマー型認知症の予防に効果がある食べ物は?
アルツハイマー型認知症の予防策として、近年注目されているのが「地中海食」です。地中海食とは、イタリアやギリシャなど地中海沿岸地域に根づく伝統的な食事スタイルで、アルツハイマー型認知症予防に加えて、生活習慣病や脳血管障害への予防効果も期待できます。
地中海食のおもなポイントは以下のとおりです。
- オリーブオイルをおもな脂質源とする(バターなどの動物性脂肪は控える)
- サバ・イワシなどの青魚を積極的に摂る
- 野菜や果物・豆類・全粒穀物を豊富に使う
- 赤身肉は控えめに、乳製品や卵は適量に摂る
- 赤ワインを少量楽しむ(※飲酒に制限のない方のみ)
これらの食材には、抗酸化作用や抗炎症作用のある成分が豊富に含まれているため、脳細胞の老化を防ぎ、血流や神経伝達の働きをサポートする効果が期待されています。
とはいえ、毎日の食事をすべて地中海食のスタイルに切り替える必要はありません。たとえば「バターの代わりにオリーブオイルを使ってみる」「週に数回は魚を食べる」「野菜と果物の量を少し増やす」といった、取り組みやすいところから取り入れてみるのがおすすめです。
まとめ
今回は、アルツハイマー型認知症の特徴や発症リスクに触れながら、日常生活のなかで実践できる予防のヒントについて紹介してきました。
アルツハイマー型認知症は、発症する10~20年前から脳に変化が起きていると言われています。そのため、予防と同じように「早期発見」も重要です。早い段階で脳の変化に気づくことにより、適切な治療や進行を遅らせるための取り組みにつなげることで、脳の健康な時間を引き延ばすことを期待できます。
『認知症と向き合う365』はMRI画像をAIで解析する「BrainSuiteⓇ」を活用し、脳の状態をより詳しくチェックすることができます。さらに希望される方は、より精密に脳の状態をチェックするFDG-PET検査を受けることも可能です(※別途費用)。FDG-PET検査では、症状が現れる前の段階から脳内の変化を確認できるとされています。
「何となく不安だけれど、どこに相談すればよいかわからない」という段階からでも大丈夫です。『認知症と向き合う365』では、医師や心理士などの専門スタッフと連携しながら、皆様の自分らしくいきいきとした毎日を過ごすための健康づくりをサポートします。
- 画像素材:PIXTA
【参考文献(ウェブサイト)】
- 厚生労働省(2015). 若年性認知症ハンドブック. [オンライン]. 2025年7月11日アクセス,
https://www.mhlw.go.jp/content/000521132.pdf - 長寿科学振興財団(2023). 医食同源とは. [オンライン]. 2025年7月11日アクセス,
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/koureisha-shokuji/ishoku-dogen.html
【参考文献(書籍)】
- 秋下雅弘(2023). 目で見てわかる認知症の予防. 成美堂出版.
- 朝田隆(2017). まだ間に合う!今すぐ始める認知症予防. 講談社.
- 朝田隆(2023). 認知症グレーゾーンからUターンした人がやっていること. アスコム.
- 朝田隆/森進(2023). 認知症を止める「脳ドック」を活かした対策. 三笠書房.
- 旭俊臣(2022). 早期発見+早期ケアで怖くない隠れ認知症. 幻冬舎.
- 森勇磨(2023). 認知症は予防が9割 ボケない7つの習慣. マガジンハウス.
この記事の監修者

佐藤俊彦 医師
福島県立医科大学卒業。日本医科大学付属第一病院、獨協医科大学病院、鷲谷病院での勤務を経て、1997年に「宇都宮セントラルクリニック」を開院。
最新の医療機器やAIをいち早く取り入れ、「画像診断」によるがんの超早期発見に注力、2003年には、栃木県内初のPET装置を導入し、県内初の会員制のメディカル倶楽部を創設。
新たに 2023年春には東京世田谷でも同様の画像診断センター「セントラルクリニック世田谷」を開院。
著書に『ステージ4でもあきらめない 代謝と栄養でがんに挑む』(幻冬舎)『一生病気にならない 免疫力のスイッチ』(PHP研究所)など多数。



